スポンサーリンク

「何言ってるの?それを決めるのはリョウ、あなたでしょう?」
テラの言う通りだった。食料となる魚は自分達で調達できる。となると、そもそも島伝いに進むのであれば、この島の人々に手伝ってもらうことはそれほどない。せいぜい水を積み込む許しをもらう程度のことで、水の豊富なこの島で断られる心配はほとんどないと言える。筏もすでに治っていて、今ケンがやっている作業は補強程度の事だった。結局のところ、島の人に途中まででも案内してもらえるのではないかとか、次に向かう島への連絡をしてもらえないかとか、本来自分達でなんとかしなければならないことなのにも関わらず、島の人達に余計な期待をしていたのだ。つまるところ、出発を引き延ばしているのは僕自身だった。
冬の食料を得る為に星屑石を携えて村を出た。その冬最初の雪がちらつき始めた頃だった。海沿いの台地から離され島ごと流されて子供四人で海を漂った。どうにか魚を獲れるようになった日々。ケンが弓を作り鳥を捕まえ、塩を作れるようになった。漂流していたラウトを救い、海賊とやり合い、筏を作って島を出る決意をした。筏で海を渡り、島を見つける。そして、嵐にあって遭難。ラウト達親子とこの島の人々に救われて、ばらばらになった筏の材料ごとこの島まで連れてきてもらった。頭の中を巡るこれまでの出来事を思い返せば、ついこの間まで大事なことは全て自分達で決断してきたはずだったのだ。
今、安穏と暮らせるこの島での生活の中で、自分が避けていたこと。いつまでも人任せにしていてはいけないことをテラははっきりと言ってくれたのだった。
地面に長い影が伸びる。夕刻が近づいていた。
テラと肩を並べて海辺の村に戻る。
「リョウ、姉ちゃん!」
ソウが駆け寄って来た。右手に弓矢を左脇に狩りで獲った鳥を携えている。
「今日も山に行ってきた。島の奴ら、皆楽しいんだよな」
弓の弦を軽く弾きながらソウは言った。
「奴って言わないの!」
すかさずテラがたしなめる。犬のコロが僕らを見つけると駆け寄って来た。僕はコロの頭をなでて小魚を一匹あげた。その場で嬉しそうにコロは食べ始めた。僕、テラ、ソウと並んで小屋に入る。ラウト親子が自分達の住まいの敷地内にある小屋を提供してくれたのだ。扉を開けるとケンが既に炉に火を起こしていた。僕は銛を壁に立てかけると一旦外に出て、獲ってきた魚の腹を開いた。はらわたを予め用意していた塩水を張った土器に入れる。つい離され島に居た時の習慣が出てしまうのだ。腐ることなく保存されたはらわたは、漁の前に魚を集める撒き餌にも食べ物の味つけに使える貴重なものだ。離され島で身に着いた感覚は、既にこだわりになっている。小屋に戻って魚に串を指すと、壺から塩を取り魚の身に擦り付ける。そして炉の脇に刺した。
ケンとテラは、既に座って炉を見つめながら談笑している。ソウは立ったまま戦い遊びをしている。敵を創造して、足で払ったり杖で突く真似をしているのだ。
「ケン、筏はどう?」
僕はケンにたずねた。
「うん、草も伸びて来たからヤギの餌も心配なくなってきたよ」
ケンが答える。僕らの筏は倉庫と非難場所を兼ねた舟を両脇に配置して、間に筏をもってきて広く身動きができるようになっている。真ん中の広い筏部分の上には土を敷いて草をはやしているのだ。ヤギの餌にするために以前考えついたことだった。嵐で舟以外は全てばらばらになったものの、この島で暮らす月の満ち欠け2回りの間に全て元通りになっていた。ケンのお手柄だった。
しばらくして魚が焼けた。手に取って食べ始める。一口食べてほっとすると、自然と言葉が口ついて出た。
「ではいつでも出航できるんだね」
僕がケンに問いかけると、ソウが横から言った。
「ずっとこの島でも良いんじゃないの。魚はいくらでも手に入るから暮らし安くて良いと思うんだよね。この島の連中、良い奴ばかりだぜ」
「奴って言わない!」
テラがまたソウをたしなめる。そして、僕とケンを交互に見比べながらこう言った。
「私は私達の村に帰りたい。例え冬の生活が大変でも家族がいる。仲間もいる。皆私達のことを心配しているはずよ」
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
最初に戻る
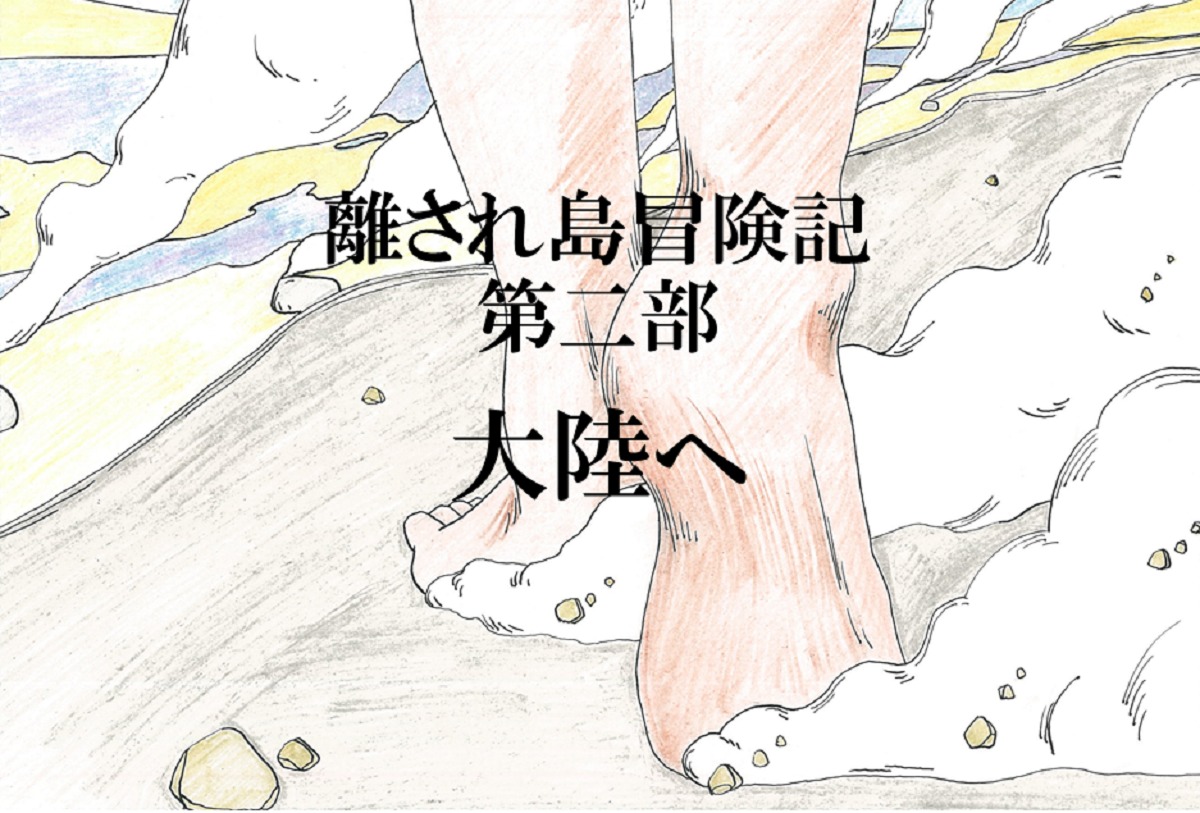


コメント