スポンサーリンク

翌朝、ラウトが中々起き上がれないという事態になった。離され島や彼の島ではいつも元気一杯だった彼がなぜこんなことになってしまったのか。
「星が見えないなんて」
夜中、ラウトの口からうわごとが漏れるのをケン、ソウ、そして僕も耳にしていた。ここ鉄炉では常に煙が漂っていて、夜の星はもちろん昼間の太陽すらぼんやりとしか見えない。僕らは既に慣れてしまっていたが、ラウトはそうではなかった。ラウトにとって、太陽や星は自分自身の立ち位置を確かめる意味で大事なものなのだ。もちろん普段の生活の中でも天気が悪くて星が見えないことはある。彼が生まれ育った島であればそれは何でもないことだ。島を離れている時はどうなのだろうか。彼ら海の民が、島が見えなくなるほど遠くの海で漁をするのは、天気が安定している時に限られている。つまり島を遠く離れる時は、太陽や星で自分のいる位置を確かめられる。だからこそ、周囲に何もない海の上でも正気を保っていられるのだった。慣れ親しんだ場所以外で星が見えない経験をしたのはラウトにとって事実上ただ一度、離され島に辿り着くきっかけとなった大嵐の時だった。今、ラウトは死の恐怖に喘いでいる。鉄炉での生活は煙と共にある。僕らにできることは、彼を見守ることだけだった。ここでは「働かざる者食うべからず」という、普段は言葉にされることのない鉄則がある。僕はラウトとソウが常に一緒にいられるように、仕事の振り分けを決める兵に頼んだ。ラウトの足がおぼつかなげであっても、ソウが一緒に行動すれば手助けができる。僕とケンが最も大変な作業を担当するという条件と引き換えだった。常に監視の目にさらされていて休む暇のない作業、それは船着き場に最も近い、鉄炉と炭焼き小屋の補助作業だった。僕とケンは鉄鉱石の受け渡しから炭の原料となる薪割、小屋や炉への材料の投入まで、人手の足りない仕事を見つけては先頭に立って作業をこなした。全体の流れを理解していないとできない仕事であったものの、僕もケンもそつなくこなすことができた。それだけここでの仕事を把握している証拠だと言える。いずれ自分達の故郷で鉄作りをしようと目論んでいる僕らにとって、それは大きな自信となった。そんな気の抜けない仕事をこなしつつ、僕らの目の端は常にある一点を捉えていた。それはクレの住まいを囲う土壁の入り口だった。
割り振り担当の兵は、リキを一目見て鉄鋼石の運搬を命じた。身体が大きく、見るからに力がありそうだったからだ。この割り振りには二つの意味がある。一つはより早くより多くの鉄鉱石を運ぶこと。運搬作業が早ければ船の出向も早くなり、その後の仕事の流れに滞留がなくなる。もう一つの理由はこうだ。鉄鋼石を運び続けるのは骨の折れる仕事だ。一日働けばくたくたとなり、その日に担当した者は夕食を済ますと倒れるように眠ってしまう。つまり反乱や逃走の心配が少なくなるのだ。リキの身体から滲みだす百戦錬磨の雰囲気は、鉄炉にいる全ての兵を振り返らせるに足るものだったのだ。非常に体力のいる仕事ではあったものの、リキは文句ひとつ言わずに作業をこなした。当初は反抗を警戒していた兵達だったが、リキの従順な態度が功を奏した。初日が終わる頃には、彼に注意を向ける兵はいなくなっていたのだった。周囲の人々と談笑しながらすっかり場に和んでいるリキの様子に、僕はあっけにとられた。なるほど、海賊の首領として生きるということは、こういうことなのだ。強さだけではないリキという男の秘めた力に、僕は目の覚める思いだった。
「あれがリキの凄さなのだな」
長くここにいるかのように悠然と僕らの前を通り過ぎるリキを見て、僕はケンに話しかけた。
「リョウ、君だって同じようなものさ。もちろん力ではかなわないだろう。けれど、相手の警戒心を一瞬で解いてしまう人としての魅力は、リキに負けてないと僕は思っているよ」
僕はぽかんと口を開けるしかなかった。あまりにも意外なケンの返事だった。
昼間の作業が済むと、リキ、ラウト、そして僕ら三人は一緒に夕食を取りながら今後のことを打ち合わせした。
「次にあの船が来る時、それが最初で最後の脱出の機会だ」
反論無用とリキの顔が語っていた。あの船とは、僕らが載せられてきた奴隷運搬船のことだった。鉄鉱石や石灰は、何艘もの船で途切れることなく運ばれてくるが、奴隷となるとそうもいかない。一艘限り、そして、鉄炉に来るのは新月から満月のまでの間に一、二度、満月から新月についても同様に一度か二度だった。ここでは月を見られる日はほとんどなかったので、はっきりと日にちを確定するのは難しい。とは言え、リキとラウトが来てから既に数日が経っていた。次に船が来るのは明日だとしてもおかしくない状況だった。
「クレの剣、あの凄い切れ味の秘密がわかっていない。もう少し何とかならないものだろうか?」
僕はリキに言った。彼は少しの間黙っていた。そして口を開くとこう言った。
「問題はラウトだ。こいつをこれ以上ここに居させるわけにはいかない」
その言葉に僕は、はっとなった。今もぐったりと死んだような眼をしているラウト。真直ぐ歩くのも怪しくなっていることから、兵からも既に目をつけられてしまっている。ソウが手助けして誤魔化すのも限界にきていた。次に船が来たら返されてしまうか、あるいは…。
「生きてここを出てこそでしょ、リョウ」
ふいに後ろから声がした。テラだった。彼女にとっては、剣の作り方などはどうでも良い事だった。ソウもテラの言葉にうなずいている。僕はケンの方を振り返った。ケンは黙って下を向いたまま、目を上げることはなかった。いずれにせよ、僕らに残された時間は限られている。それだけは、はっきりとした事実だった。
翌日、鉄鉱石を積んだ船が数艘同時に到着した。船着き場はごった返していた。どの船主も自分達が運んできた鉄鉱石を先に降ろしてほしいと兵に詰め寄っていた。リキはもちろん僕やケンも、何より鉄鉱石の運搬を最優先にして動くこととなった。人と荷車が混ざり合い、混み合っていた。いつ事故が起きてもおかしくない。僕は周囲をしっかり見るべく顔を上げた。
「どっかーん!」
そこにいた全ての人々がはっとして立ち止まった。荷車同士がぶつかる音だとすぐにわかった。土壁の中に鉄鋼石を運び込もうとしていた荷車の真横に、別の荷車が突っ込んでいた。ぶつかられた方の荷車を押していた男は倒れていて、痛そうに足を押さえている。もう一方の男は茫然と立ちすくむようにそれを見下ろしていた。身体の大きいその男はゆっくりこちらを振り返った。リキだった。僕らは一瞬目が合った。僕は何も考えることなく、ただ身体が動くのに任せた。気がついたら全力で走っていた。運び手を失った荷車に辿り着いて右の押手をつかんだ時、もう一本の手が同じく左の押手を握るのが見えた。ケンだった。僕らは同時に荷車を押し始めた。二人で押すことで、荷車は滑るように早く進んだ。クレが住む敷地を囲う土壁の門は、荷車を受け入れるべく開いていた。その門に向けて僕らは一気に荷車を進めた。土壁が眼前に迫った。そして入り口を守っている兵が逡巡している隙に、僕らは一気に門を潜ったのだった。
つづく
別のバージョン
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
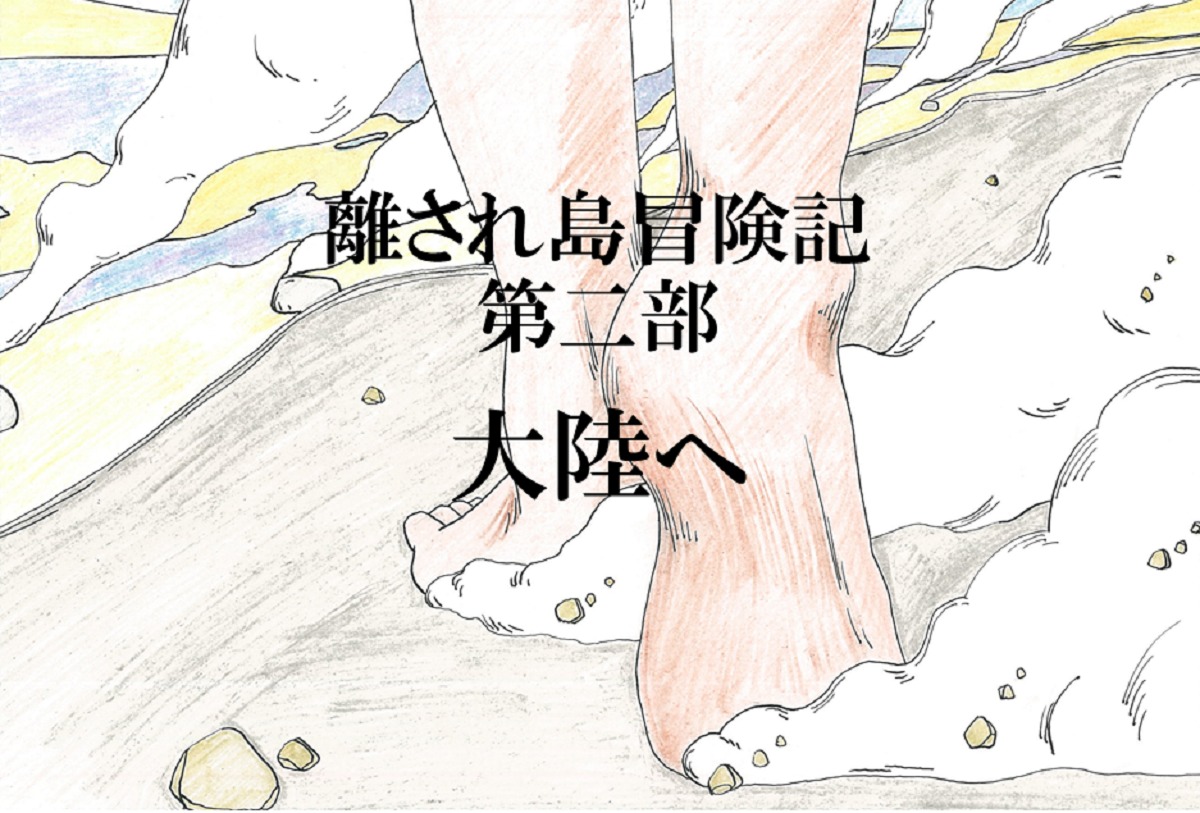

コメント