スポンサーリンク

「リキはどうした」
ポンチョの脇に佇む影が尋ねるように言った。
「もうすぐ来るさ」
吞気そうにガリが答えた。
「それならば急がねばな」
影の口元に白いものが浮かんだ。その手にする剣の先はポンチョの背中に向けられている。ポンチョの足には縄がかけられていて、そこから動けないようにされていた。
「ガリ、すまん。こいつらあっさりと裏切りやがった」
ポンチョが喉から絞り出すように声を発した。
「なに、そんなこともあらあな。だがな、裏切ったと言っても所詮は船長と二人の兵位だろう。残りの船員は、そもそもが身寄りのない使われるだけの人間に過ぎない。いざとなればどっち着かずだろうよ」
ガリの言葉に影が一瞬動揺した。その時だった。何も言わずに身構えていたソウが虚をつく行動に出た。手にした剣を影に向けて思い切り投げたのだ。くるくる回りながら空を切って飛んだ剣は、ポンチョと影の間の木でできた甲板に音を立てて突き刺さった。影は驚きのあまり数歩後ずさりした。その隙をついて、ポンチョはソウの投げた剣を拾い上げ、自らの足を縛っていた縄を切った。そうなると、そもそもが丸く堂々とした体格のポンチョなのだ。剣と自由を手に入れた途端に船上での存在感が増して、敵味方の力関係は逆転してしまった。後ずさりする兵達に対して、ソウは間を置くことなく手元にあった剣の鞘をポンチョに投げ渡した。そして、そのまま船内を走り船縁に置いてあった櫓を手にしたかと思うと、頭上で大きく回したのちに身構えた。
「鉄炉に連れられて来られる時に乗った船だからな。どこに何があるかなんて、お見通しさ」
敵と相対するこの状況にも関わらず、ソウの表情はどこか晴ればれとしている。
「自ら剣を手放すとは!そんなことをして勝てると思っているのか?」
影、つまり船長と二人の兵は驚き怯みながらも、櫓を構えるソウをあざ笑った。
「なに、こちとら棒切れの方が戦い慣れているのでね」
言葉を発すると同時に、ソウは甲板の一番高い所に一気に駆け上がった。そして、帆を止めている縄を手にすると弾みをつけて兵の一人に向かって跳躍した。慌てた兵は剣を身構えた。だが、兵の近くに着地したソウは低く構えると、剣の隙となる兵の足元めがけて櫓を一閃させた。兵は硬い櫓に足をすくわれて甲板に転がった。すぐさまその腹に櫓を叩きつけるソウ。防具が割れる音がして倒れたまま兵はうめき声をあげた。兵の手から転がった剣を拾い上げると、ソウはその剣をテラに向かって投げた。
「姉ちゃん、コウとサイを頼む」
「わかった」
テラが答える。女の子とはいえ、万が一の戦いに備えて、旅の間に訓練をしていたテラであった。剣を構える姿が様になっている。事の成り行きにただ呆然としていたコウとサイに笑みが戻った。
「相変わらず早いな、お前の動きは」
ポンチョがあきれたようにつぶやいた。ソウはにやりと笑った。
「さて、これで二対四だ。まだやるのかい、船長。それにもう一人の兵さんよ」
ガリが言った。リキの手下とはいえ、やはり百戦錬磨の海賊なのだ。味方として剣を手にしたガリは、これまで見たどんな時よりも強く、頼りがいがあるように感じられた。
中央に逃げを図ろうとするケンの手はクレによって阻まれた。右辺の集団を生かすには右下隅にあるクレの黒い一団を獲る以外にない。ケンは右下隅に手を放った。ここにあるクレの石は全部で九つ。これに応じなくては全て獲られてしまう。その上、右下隅のとても大きな領域が全てケンのものになる。クレが打つ手は一つのはずだった。今や鉄炉中の人間がこの勝負を見るために集まっていた。周囲を守る兵の存在に怖くて近寄れないものの、離れたところから円形に僕らを囲んでいる。なぜか、台地に上がる階段にすら人が鈴なりになっている。沢山いる兵達の目も全てがケンとクレの白黒勝負に釘付けになっており、階段を占拠する人達に気が付いていないのだ。今や逃げようと思えば誰でも逃げられるのではないかと思えるほどのこの状況だったが、動く者は誰一人もいない。そしてここにいる人々の全てが、クレの次の一手は右下隅のある一点しかないと考えている。皆が息を飲んで次の手を待っている。何一つ音がしない。普段なら夜通し行われる炭焼きや鉄を作る作業も完全に止まっている。鉄炉を包む煙が薄くなっていることに、この時になってリョウは気が付いた。その時クレの手が動いた。黒石を取り上げて、当然右下隅に置かれると思われていたその手は、なんと右上にあるケンの集団を制限する手だった。
「うおー!」
周囲で見ていた全ての人々が叫び声をあげた。黙って盤を見つめつづけていたのは、対戦しているケンとクレの二人だけだった。
「リョウ、どういうことなんだよ?クレはあの石を捨てたのか?さっぱりわからねえ。なあ、もうケンの勝ちは決まったも同然なんだろう?」
リキが大きな声で問いを発した。流石のクレも顔を上げてリキをにらんだ。
「いや、クレは右上を制する方が大きいと考えたのだ。これを受けないと、確かに右上で生きを図るための厳しい戦いとなりそうだ。かといって、右下隅も完全に制するにはあと一手必要だ。どちらを選べば良いのか、これは悩ましいよ」
僕はケンとクレの戦いの邪魔をしないように小さな声でささやいた。するとその時、ケンが右下隅に石を置いた。その瞬間、右下隅の九つの黒石と、本来は白と黒で分け合われるはずであったその辺りの領地は全てケンのものになった。周囲の人々は再びどよめいた。
「おい、これでケンの勝ちだろう?あの大きな集団を獲ったんだ。もう決定に違いないよな」
リキが興奮して更に大きな声を出した。
「うるさい、黙れ!おい、誰かそこのでかいのを鉄炉から追い出してしまえ!言う事を聞かないならば切れ!」
クレが周囲にいる兵に命令した。
「は!クレ殿。直ちに連れ出します」
四、五人の兵がクレに敬礼したかと思うと、こちらにやって来てリキを取り囲んだ。
「おいなんだよ!勝負を最後まで見せてくれよ」
リキが叫ぶ。
「黙れ、お前は鉄炉から追放だ。すぐに出ていけ!」
兵の中でも最も地位の高い者が先導して、台地に上がる階段に向かって歩き出した。階段を埋め尽くして勝負を見ていた群衆が道を空ける。
「おいおい、待ってくれよ。最後まで見せてくれよ」
リキが両脇を抱える兵に頼む声がむなしく響き渡る。
「何を言うか。お前のせいで次の手を見逃すことになるかもしれないのだぞ。そうなったらすぐさま切り殺してくれようぞ」
聞こえてくる兵の声がなんともこっけいで、周囲の人々から笑いがこぼれた。鉄炉から人が出て行くのは、ある意味で脱走と同じ。本来なら即座に処刑されるはずなのだ。そしてリキもまた、鉄炉を出られるのは喜ばしいことのはずなのにすっかり白黒の虜になっており、ここに留まりたいという。そんなリキに僕は苦笑するしかなかった。
「リョウ、河沿いを下れ!夜明けまでそこで待つからな」
台地に上がる最後の瞬間にリキが叫んだのが聞こえた。それにしても、この状況にも関わらず自ら逃げ出す人がいない。そして鉄炉がこれほど混乱していても、盤上以外のことが眼中にないクレ。僕はこの勝負が人を惹きつけるすさまじさに、改めて驚きを感じずにはいられなかった。
「まだ勝つものと思っているようだ。まあ良い。ようやく静かになった。これほど心躍る戦いは我が人生で初めてだ。存分に楽しませてもらうぞ」
にやりと笑うとクレは石を置いた。先の石から中央に向けて一歩進んだのだ。この展開を見て、僕の掌に汗がにじみ始めた。一見、ほんの小さな一歩にすぎないようにも見える。それにも関わらず、しっかりとケンを狭い場所に閉じ込めることに成功しているのだ。そしてこの石と既に左上隅に置かれていた石とが相まって、未開拓だった上辺が将来の黒の陣地として大きく主張し始めることとなった。更には自らの右辺の石に広がりと中央進出の足掛かりをも与えている。ただ一手で、これまでケンが築いてきた陣地全てを遥かに上回るかのような大きな模様が盤上に描かれてしまっていた。クレの手はそれほどまでに効率良く、強い一手だった。右下隅で大きく陣地を稼いだことで序盤にして勝ちが見えたかのようなケンであったが、それはつかの間の話だった。閉じ困られた石達が助けを求めて震えているのがわかる。窮地に立たされたケン。今やその頬は青ざめ、背中に現れた汗が徐々に広がりつつあるのが、夜陰の中ですら、はっきりと見て取れた。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
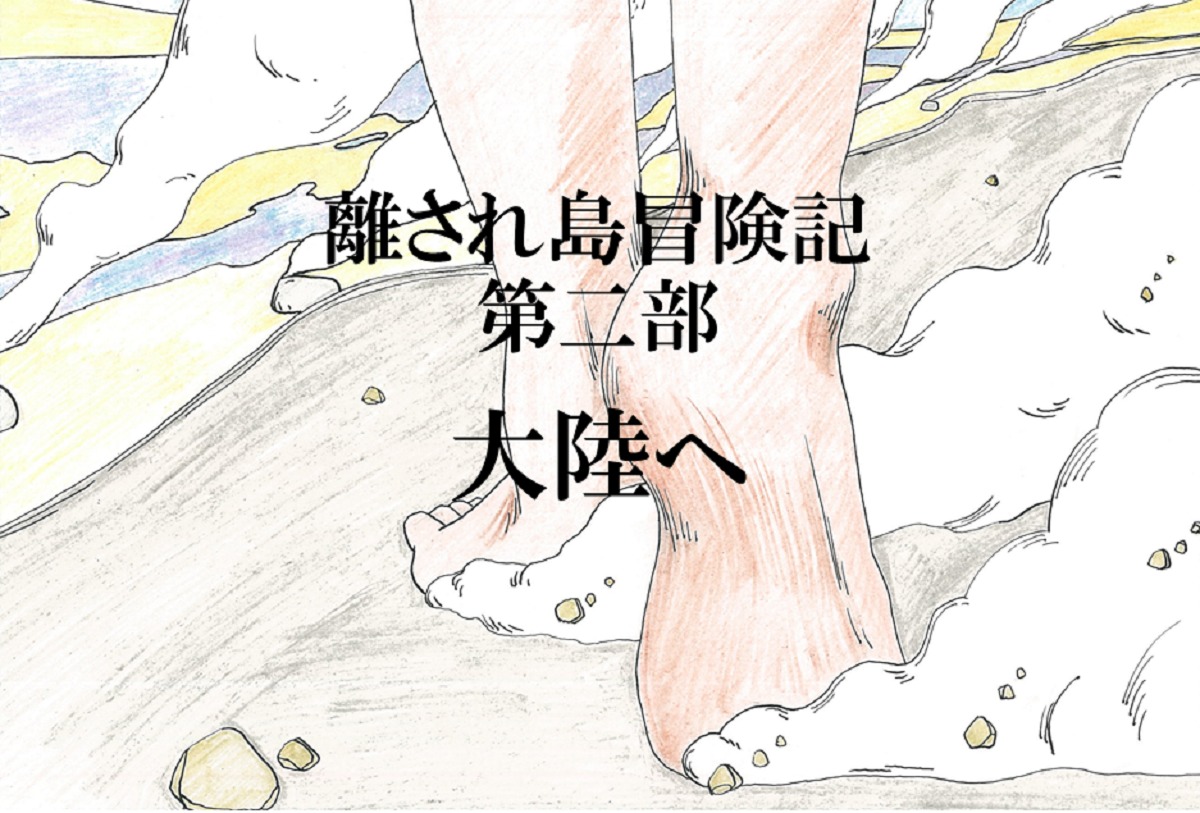

コメント