スポンサーリンク

「ラウト行くよ」
僕とケンはラウトの脇に肩を入れて身体を持ち上げた。一歩、また一歩と階段の登り口に近づいていく。遠くから聞こえてくる兵達の足音に胸の音が高まるのがわかる。
「兵が来る。急げ!」
後ろからリキが声をかけてきた。律儀に順番を守って僕らの背後を守ってくれている。しんがりを務めるはずのリキだったが、二人の兵を倒したことで既にいつでも退去できる体制が整っていた。
「リキ、先に逃げてくれ」
ラウトの身体を抱えていて速く移動することができない。後ろを振り返る余裕がないまま、僕はリキに声をかけた。
「何の為に鉄炉に来たと思っている。お前達を置いていく訳には行かねえんだよ」
イライラするようにリキが言った。僕らもやっと階段の登り口に到着した。見上げるとソウと女の子達が台地の縁に到着したのが目に入った。
「ソウ達は逃げ延びた。もう充分だ。リキ、先に行ってくれ!」
僕は叫んだ。
「ちっ、仕方がねえな」
リキは僕らの前に回ると先に立って階段を数段上り、振り返ると手を差し出した。ラウトを引き揚げようとしてくれるのだ。とその時、ついに兵達がやってきた。
「脱走だ!」
兵が大声を上げた。
「リキ、剣を貸してくれ。僕がくい止めている間にラウトとケンを頼む」
僕は右手をリキに突き出した。リキは苦虫を嚙み潰した顔をしたかと思うと突然飛び上がった。リキの大きな身体がケン、ラウト、そして僕の頭を越えたかと思うと、階段の下に着地した。
「お前では無理だ」
立ち上がると、振り返ることなくリキは剣を抜いた。数人の兵が同じく剣を抜いて向かってきた。振り下ろされる剣をリキの剣が払いのけた。鉄と鉄がぶつかる音が崖にこだました。リキの剣さばきに怯む兵。が、一人の兵が勇敢に向かってくる。その顔には見覚えがあった。
「リキ、昼間僕らを助けてくれた人だ。殺したりしないでくれ!」
「そんな余裕は無い。こんな時に何を言ってるんだ」
リキの返事は当然だった。
「いいから、お前達はさっさと上に行け!」
背中からリキの叫びが聞こえた。リキも、その兵も僕らを助ける気持ちに変わりはないとも言える。出来ればどちらも助けたいとの思いがある。それでも今すべきは皆を逃がすことだった。僕とケンは力を振り絞ってラウトを抱え上げた。平地と違い、ほとんど歩けなくなっているラウトを持ち上げるのは骨の折れる作業だった。常日頃も重い物を運び上げている僕らだったが、ぐにゃぐにゃする人の身体がこんなにも運び辛いものだと初めて知ったのだった。その時だった。
「ひゅん!」空気を切る音がしたかと思うと、頭上の階段に数本の矢が刺さった。振り返ると、そこには弓矢を携えた幾人もの兵と、それを率いるクレがいた。
「そこまでだ」
僕らが怯んだ様子を見て、ゆっくりとクレが言った。
「行け!」
リキの声が聞こえた。クレめがけて走りながら、リキは剣を振りかざした。兵の意識を自分に引き付けようとしての行動だった。クレが来た途端に諦めの気持ちが芽生えた僕らだったが、それを見てまた急ぎ階段を登り始めた。背後で剣と剣がぶつかる音がした。クレがリキの剣を自らの剣で受け止めたのだった。
「ほお、強いな」
クレは言った。
「おのれ!」
配下の兵がリキめがけて剣を振り上げるとクレは左手で合図してそれを止めさせた。その隙を見て、リキは再度クレめがけて剣を振り下ろした。
「キン」
一際高い音がした。クレがリキの剣を横から薙ぎ払ったのだ。驚いたことに、リキの剣は無残にも真二つに折れていた。呆然とするリキ。
「お前、ここにいる兵の誰よりも強いかも知れぬな。だが剣の差が出た。残念だったな」
立ちすくむリキを尻目に、クレは兵達に僕らを捕まえるように指示を出した。雪崩のように階段を駆け上がって来た兵達に僕らはなすすべもなく捕まり、階段を引きずり降ろされた。
僕らは兵達に抑えつけられて、顔を地面に擦り付けられた。クレの足が横に立つのが目に入った。
「ふむ。兵を二人、瞬時に倒したようだな。おい、誰が介抱してやれ」
クレが言った。数人の兵が、倒れていた兵を担ぎ上げて運んでいった。
「良し。見せしめに殺すのはその弱り切った奴だけにしてやろう。おい、強いの。お前は我が兵になれ。残りの二人は、今後一切、共に行動してはならぬ。一人は今まで通り、もう一人は一生の間、俺の剣だけを作るのだ」
クレが言った。つまり僕かケンのどちらかがクレの秘密の工房で働き、リキは兵に、ラウトが見せしめの死刑という命令だった。僕は一言も返すことができず、ただ、地面に顔をうずめていた。
「それはできない相談だな」
その声が聞こえた途端に、リキを抑えつけている兵達に動揺が走るのが感じられた。数人に抑えられているにも関わらず、徐々にリキが起き上がっていく。僕らを抑える兵にも動揺が走り、身体を抑える力が緩むのがわかった。顔を持ち上げることができるようになって、目の前で起きていることが目に入って来た。兵を蹴散らしてついにリキが立ち上がった。その様子を見て苦笑するクレ。
「ラウトを死なせるわけにはいかねーんだよ」
顔についた土を払いながらリキが言った。
「残念だな。その強さ欲しかったが、それではお前が死ね」
クレが剣を構えた。クレの腕は言うまでもなく鉄炉一。素手のリキに勝ち目がないことは明白だった。僕は諦めて視線を下げた。リキが切られるのを見たくはなかった。
「待った。白黒で勝ったら何でも言うことを聞くと、あんた、ほざいていたよな」
リキの言葉にクレは目を丸くした。そして、リキの言わんとするところを理解するとにやりと笑った。僕も驚いて顔を上げた。
「まさか俺と勝負すると?お前の腕はそっちのリョウとかいう奴に九子置きの初心者。しかも、手心を加えてもらってようやく勝負になる程度だったはずだが?」
クレの嘲笑にリキが歯噛みをするのがわかった。
「たかが、石置きの遊びだろう。やってみなけりゃわからねーんだよ」
リキは一歩前に進んだ。
「待って!」
思わず僕は声を上げた。
兵の力が更に緩むのがわかって、僕は立ち上がった。そして、リキとクレの間に割り込むと言った。
「僕が勝負します」
剣を持つクレの手に力が入るのがわかった。僕は切られる覚悟をした。
「ふむ。今まで勝負をしたことは無かったが、お前はそこそこ打てそうだ。だが、何をかける?負けたらお前が死ぬと言うのか?」
クレの言葉に背中が震えた。
「負けたら好きなようにしてください。でも、もし勝ったら僕らを自由にしてほしいのです」
僕は言った。実際のところ、万に一つでもクレに勝てる可能性は無かった。クレの白黒勝負を何度も見ていて、僕はそのことを充分に理解していた。だが、仲間が生き延びさえすれば良い。今はそのことだけしか考えられなかった。僕はクレの目を真直ぐ見返した。長い時間が過ぎたような気がした。クレの表情が一瞬動いたと思ったその時、肩に手が置かれるのを僕は感じた。
「やるよ、僕が」
ケンだった。クレが怪訝な顔をするのがわかった。
「ケン」
僕は思わずケンに声をかけた。
「リョウ、皆の為にも君は生きなければならない」
ケンは足元を見つめたまま言った。僕らのやり取りを聞いていたクレが口を開いた。
「お前がだと?白黒勝負をしているのを見たことがないが?」
クレの問いにケンはうなずいた。
「ええ、でもやらせてください。リョウより僕の方が、たぶん・・・強い」
僕は反論できなかった。鉄炉で行われる白黒をケンはいつも傍から見ているだけだった。だが、勝負を見つめる時のケンは声をかけても反応が無く、心全てを奪われているのは明白だった。そして、時々口をつく勝負所についての指摘は、明瞭且つ的確で反論の余地がないものだったのだ。何より、目の前で勝負すると言っているのがケンであるということ。それ以上の理由は不要だった。僕は黙って一歩引き下がった。
「初めての奴と打てと俺に言うのか、お前は」
クレが言った。
「あなたの腕は知っています。でも何千回、いや、何万回、僕は頭の中で白黒勝負をしてきました」
ケンは静かに返事をした。俯いてはいるものの、その目に動揺は見つけられなかった。
「白黒の石と版を持て」
クレが兵に命じた。兵の一人が走って行ったと思うと、間もなくクレ専用の石と版が運ばれてきた。
「楽しませてくれよ。いや、楽しめるかも知れぬな」
そう言うと、クレはしゃがんで白黒の版についた。続いてケンも、もう一方の側に座り込んだ。ふと周囲を見回すと、鉄炉中の人間が遠く円形に僕らを取り囲んでいた。
「お前の先手で良いぞ。なにせ初めて石を持つのだからな」
クレが言うとケンは白い石が入った入れ物を手繰り寄せた。蓋を開けて石を一つ取り出すと一呼吸の後、ケンは盤上に石を置いた。初手は僕らから見て右上隅。最も一般的な最初の一手だった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
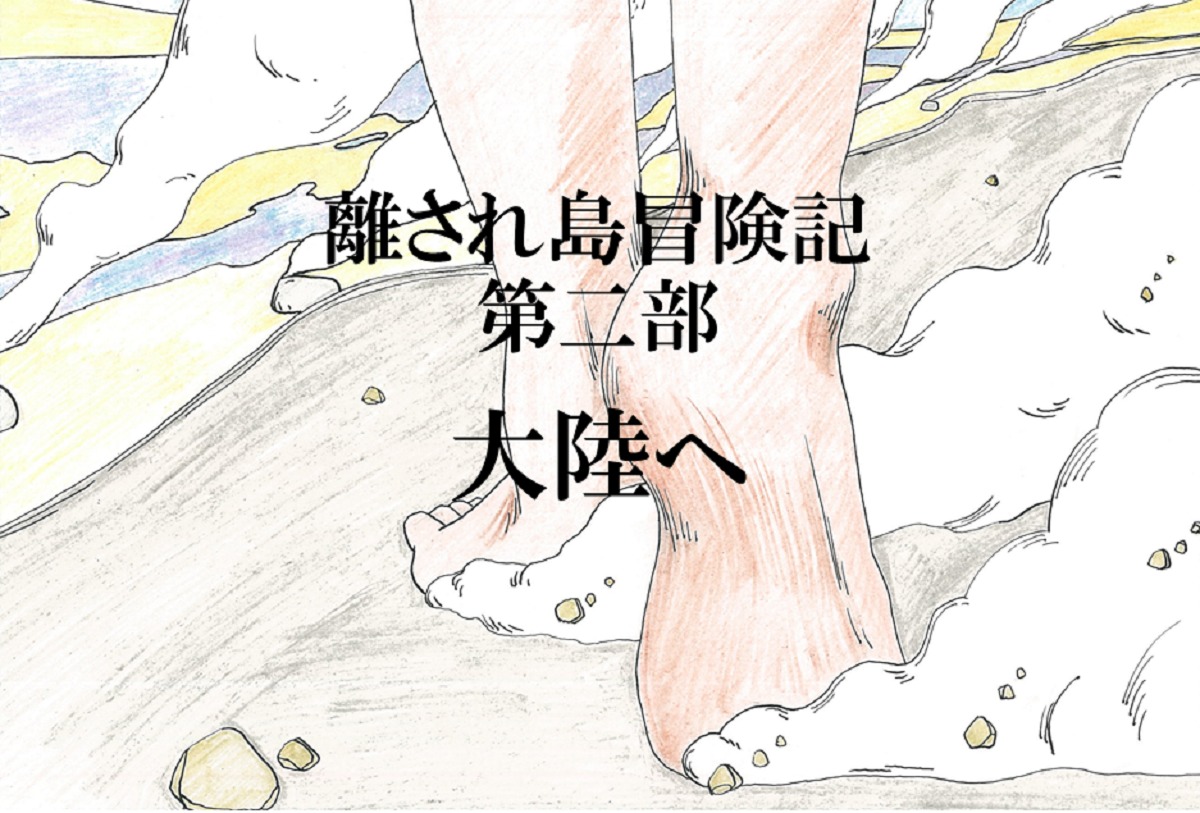

コメント