スポンサーリンク

数日の間、僕の帰還を知った友人達の訪問が続いて、何もできないまま時間が過ぎた。しかし、せっかくやって来た友人達に離され島やラウトの島、そして、大陸と帰り道での出来事を話そうとしたところ、旅の話は以前聞いたから別に良いよと何人もから言われる始末だった。僕らが必死で乗り越えてきた様々な経験も、彼らにとっては毎冬の旅とその延長程度の事でしかなかったのだ。そもそも食糧確保のための旅という、この雪深い山の村で冬越えに必要な行いそのものが、彼らにとっては一部の男衆が成しているだけの余計な事でしかなかった。実際のところ友人達の目的は、大陸からやってきたコウとサイの姉妹を一目見たいという点に集中していた。挨拶やちょっとした言葉を話す度に、友人達は上手だと二人をもてはやした。最初は戸惑っていた姉妹も、若者達の和やかな雰囲気に囲まれて徐々に慣れていったようだった。僕の母さんとのやり取りを通して、テラとは違う年配の人への言葉遣いや配慮も憶えていった。あの過酷な鉄炉において、幼い頃から大人に混じって働いていた経験は、ここでも充分に生きていた。見る間に順応していく二人の姿に、僕はほっとして胸を撫で下ろした。
スポンサーリンク
久しぶりに誰一人訪ねて来ない午後、僕は出掛けることにした。コウとサイもついて来ると言う。母さんもたまには気晴らししてきなさいと快く見送ってくれた。目的地はケンの家だった。ラウトがどうしているのか気になるのだ。ラウトの島に比べて、我が村の春は寒い。風邪でも引いていなければと心配はつのっていた。あいにく二人は家には居らず、ケンの母親によれば、連れ立って朝から出かけているということだった。あちらにいるみたいよと指さされたのは、村から見て日の出の方向、やや離れた所にある高台だった。
「行ってみるかい?」
僕が訊ねると姉妹は期待に満ちた目をしてうなずいた。
高台に近づいて行くと、響いて来たのはケンでもラウトでもなくソウの声だった。サイの顔がほころんだのがわかった。姉妹に手を貸しながら断崖の緩やかな所を選んで台地に上がった。そこにはケンとラウト、そして、ソウの笑顔があった。ケンの弟と妹もそばで遊んでいた。ほんの数日振りなのに、不思議と懐かしく感じた。僕らを見つけるとソウが駆け寄って来た。
「久しぶり。お腹空いてない?」
「久しぶり。大丈夫だよ」
ソウは真先にサイに話しかけた。互いの目から喜びが溢れていた。後ろの方からケンがこちらに手を振った。彼には珍しく笑顔になっており、その視線はコウに注がれていた。コウもまたケンを見ていた。地面には大きな穴が四つ空けられていた。半身を中に突っ込んで穴を掘っていたラウトが、立ち上がって片手を上げた。
「リョウ、コウ、サイ、元気だった?今、星を見る塔を建てているのだよ」
嬉しそうにラウトが言った。ソウとケンも嬉しそうにうなずいていた。
「星を見る塔か。良いね。村は山に囲まれていて低い星が見え辛いから、建てるならここが最適だね」
僕はラウトとケンに向かって言った。二人は僕の言葉に喜んで、互いの肩を叩いていた。
その午後以来、僕らは毎日その高台に集まるようになった。高台と接している山の裾で大木を切り、転がして運んできた。幹の太い方を穴に落し、先端に縛り付けた縄を皆で引いて一本ずつ立てていく。周囲の地面を叩いて固めると、梯子を付けて誰でも上がれるようにした。最上部に細い丸太を運んで縄で括り付ける。星を見るには平らな床が必要なのだ。大人の手を借りられないので時間はかかるものの、長い旅で培った仲間意識で乗り切った。そうこうするうちに、ラウトとケンの妹が次第に仲良くなっていった。にこにこ笑いながら話しをする二人を僕らは遠巻きに見て邪魔しないようにした。ただ一人テラだけは、いつまで経ってもその高台に現れることはなかった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
前話に戻る
1話に戻る
第二部1話に戻る
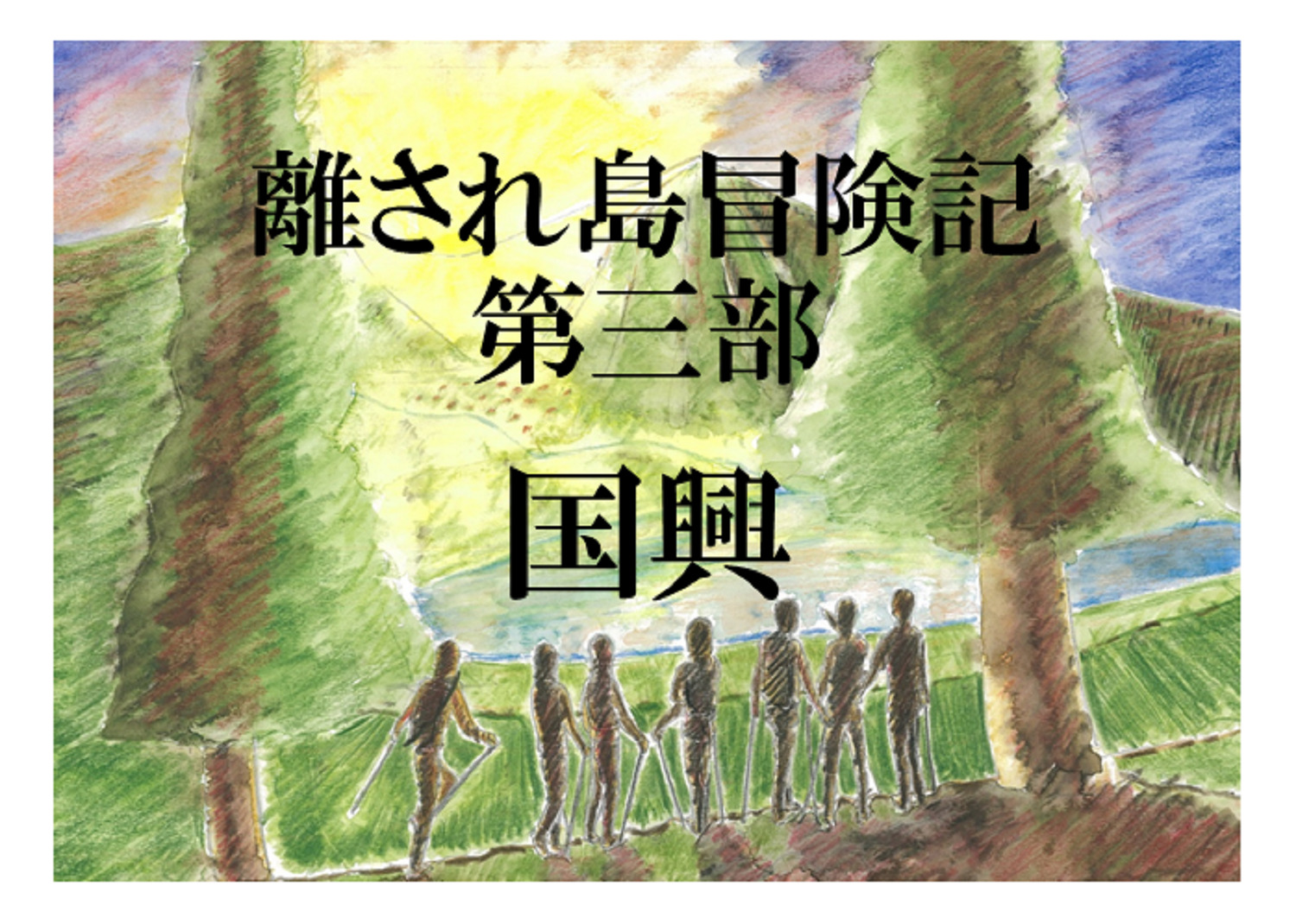

コメント