スポンサーリンク

「お前らを騙した屋台の奴らな、呆然としていたぞ」
リキは笑いながら言った。
その夜、突然目の前に現れたラウトとリキを囲んで、ささやかな祝宴が催された。宴といってもいつもと同じ魚の入った米がゆなのだけれど、テラが残り物を持って来てくれたのだ。底をさらった米がゆはややしょっぱいものの、細切れになった魚たっぷりの意外なおいしさだった。
「ポンチョとガリ、助っ人を頼んだ男達数人、それに俺とラウトで屋台の食い物を残らず平らげたのだ。食い終わると、ポンチョらと男達は、払いは俺だと主人に告げてその場を去った。俺とラウトは重くなった腹をさすりながら最後に差し出された茶を飲んだ。ゆっくりとな。そして、もみ手をしながら金を請求してきた主人に俺は言ってやったのさ。金など無いってな」
聞いている僕らも唖然とする内容だった。
「それでどうなったの?」
ソウが話の先を即した。
「主人はきょとんとして何も言わずに戻って行ったよ。少ししてようやく事態が飲み込めたのか、食い逃げだと騒ぎ始めた。俺は逃げてないってのによ」
そこまで話すとリキは大笑い。取り囲んでいる僕らも顔を見合わせて笑った。
「目論見通り、兵がやってきて俺とラウトに縄をかけた。あとはここまでのんびり船旅を楽しんだってわけさ。主人は兵から僅かな礼金をもらっていやがったが。なに、たった二人分だ。ありゃ大損だな。俺達を見送る時のしまりのない顔、お前らに見せたかったぜ」
リキがにやりと笑う。屋台の人達に騙されて鉄炉に連れて来られた僕ら。リキの話を聞いて溜飲が下がる思いだった。
「そりゃ良いや。あいつ等の驚く顔が見たかったな」
ソウがうれしそうに言った。
「それでラウトはともかく、リキはどうしてここに来たの?」
何につけても理解の速いケンがリキに訊ねた。
「当然だろ。お前達を助けに来たのさ」
リキはニヤッと笑った。皆が驚いて顔を見合わせた。そんなことができるのかと疑問を持つものの、彼が言うならなんとかなるのかもしれない。リキはそういう雰囲気を持つ男だった。
「離され島ではお前達に世話になったからな。見て見ぬふりをしたら男が廃るだろう」
リキの言葉にテラの目が輝き、頬に赤みが差すのがわかった。
「少しだけ待ってくれないか」
横から声がした。ケンだった。
「リョウ、クレの剣がどうやって作られるのか、それだけは見ておきたいと思わないか?」
ケンは強い視線をリキから僕の方に移すとこう言った。急に話を振られて僕は返事に窮した。クレの剣は確かに凄い。けれど、乱造とは言え剣の作り方と鉄の精製方法を僕らは既に憶えていた。
「これまでに憶えた作り方だけでも充分だよ。星屑石に比べたらずっと強い武器の作り方を僕らは身に付けているのだから」
僕はケンに言った。
「それはそうだ。でも、鉄の武器が作れたとしても、いずれは誰もが同じことをできるようになるに違いない。その時生き残る道はただ一つ。最も優れた物を作れるだけの技術を身に付けることが絶対に必要なのだ」
僕は何も言い返せなかった。ケンの言う通りなのだ。鉄炉にいる兵よりも作業をしている男達の方がずっと数が多い。自分達が作らされている剣で兵と戦うことだって、やろうと思えばできるはずなのだ。そうならないのは、クレが誰にも知られずに住まいの中で作らせている正体不明の剣。その威力を目の当たりにして恐れているからだった。この先幾多の困難が行く手に立ち塞がろうとも恐れずに切り抜けるためには、絶対の自信となる最高の技術を身に付けることが不可欠なのだった。それにしても、常に次の次、そのまた次を考えているケンの凄さを僕は改めて知った。
「どっちでも良いぜ」
リキの張りのある声が響いた。僕らはリキの方を振り返った。
「ここから逃げる機会は次に船が来る時だ。ほら、お前らも乗せられたあの奴隷船さ。船にはポンチョとガリも乗っていて、船長には既に話が通っている。そもそも助けに来るのが今になったのは、その手はずを整えるためだったのだからな」
力強い声に背中が震えるのを僕は感じた。リキの計画がおぼろげながら見えた気がした。
「星が見えない」
ずっと黙って聞いていたラウトがふいにつぶやいたのは、その時だった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
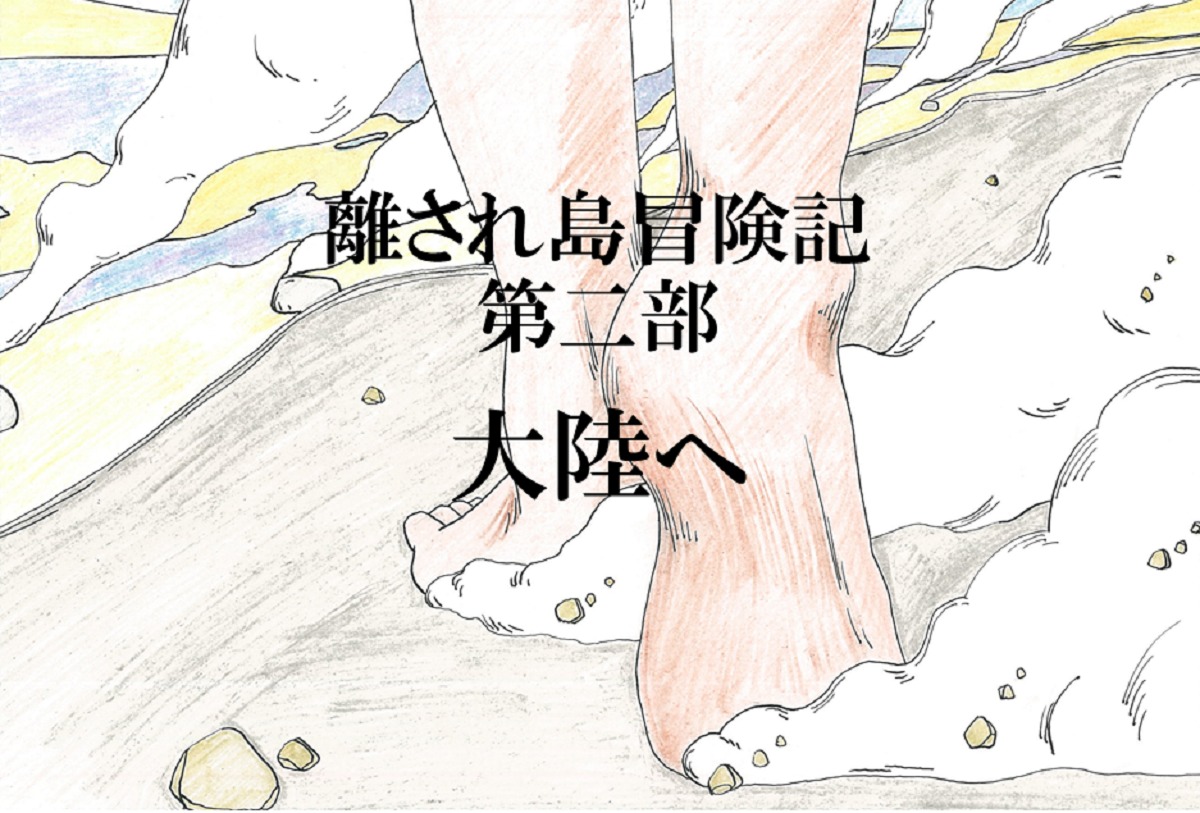


コメント