スポンサーリンク

テラ、ケン、そしてソウの寝息が耳に付く。僕は夕食時にした村に帰る話が頭の片隅に引っかかって眠ることができなかった。暮らしやすさで言えば、ラウトのこの島は山の麓にある僕らの村に比べてとても暮らしやすい。海に囲まれていて冬でも暖かいこの島では、食べ物の心配をする必要がないのだ。単に自分達だけの事を考えれば、この島に居続けるのが良いように思える。幸い島の人々も僕らの事を受け入れてくれている。以前立ち寄った島でも感じたことなのだけれど、余所者を受け入れる懐の広さがこの暖かい島にはあるようだ。僕らの村ではこうはいかない。余所者が来れば、星屑石を盗みに来たのではないかと疑うのが常だったのだ。住める土地を探して移ろい行く人々を受け入れることもなかった。何せ、冬は自分達の食料を得るだけでも大変な思いをしていたのだ。だが、その冬の食料を得る旅の途中で僕らは離され島と共に流された。一緒に旅をしていた男衆の安否もわからない。例え生きていたとしても、村に持ち帰る食料はいつもに比べて格段に少なかったことだろう。村の皆が心配だ。
「どうしているのだろう」
つい言葉が口をついて出てしまった。
「リョウ、眠れないのかい?」
隣で寝ていたはずのケンの声がした。
「うん、村のことを思い出していたのだ」
僕は答えた。
「さっきはああ言ったけど、筏は大丈夫だよ」
ケンの言葉に、僕は彼の方に身体の向きを変えた。
「それもわかっているよ」
僕の返事にケンはつむっていた目を開いた。
「用心するに越したことはないよ。先ず、ラウト達に僕らの気持ちを伝えて意見を聞いたらどうかな?」
ケンの言葉に僕は半身を起こした。
「ケンも帰りたいのかい?」
「当たり前だよ。僕にだって父さん母さんはもちろん、弟や妹もいるのだ。会いたくないわけがないだろう」
ケンの言葉を聞いて、僕も家族一人一人の顔を思い浮かべた。
「冬を乗り越えて、本当に皆生きているだろうか?」
思わず弱音が漏れた。すると炉を挟んで反対側に寝ていたテラが言った。
「帰りたい。皆に会いたい」
ケンは黙ったままだった。
「そうだね」
僕はテラに言うともなくつぶやいた。
炉に残っていた薪がぱちんと爆ぜる音がした。それを合図にケンもテラも再び目をつむった。静かな夜に包まれて僕も眠りに落ちて行った。それでも微かに聞こえる波の音が僕の心を揺さぶり続けていた。
夜が明けた。炉の炎が強くなる気配があった。テラが朝食の準備を始めたのだった。ケンとソウはまだ眠ったままだ。僕は起き上がり、土器に溜めた水で顔を洗った。漁の準備をしようと扉を開けると犬のコロがすぐ前で寝ていた。危うくつまずきそうになりながら小屋の外に出ると、ラウト親子が夜風に当てて干していた釣り道具を取り込んでいた。どんな道具でもそうだけれど、丁寧に洗って、拭いて、乾かすことで道具は長く使うことができる。この親子は見るからに道具を大事にしている。道具を大事にする者は人も大事にすると僕は父さんから教わってきた。ラウト親子を見ていると、彼らは信頼できると改めて確信するのだった。
「おはようございます」
僕は二人に近づいていって声をかけた。
「おはよう」
ラウトが笑って返事をした。ラウトのお父さんは笑顔で右手を上げて答えた。僕はもう一歩進んで言った。
「相談があるのですが、今よろしいですか?」
僕の言葉に二人は一瞬顔を見合わせた後、頷いてくれた。
「そろそろ僕らの村に帰りたいと思うのです」
単刀直入に僕は言った。
「まだ早い。もう少し待ちなさい」
ラウトのお父さんは即座に答えを返してきた。そして先ほど取り込んだ釣り道具を持つと、唖然とする僕を置いてすたすたと海の方に向かって歩いて行ってしまった。
「ごめん、後でまた話そう」
ラウトはもう一つあった釣り竿を右手でつかむと、僕に向かって軽く左手を上げ、父親を追いかけて走っていった。
「どうだった?」
振り返るとケンとテラが小屋から出てきてこちらを見ていた。
「ラウトのお父さんはもう少し待てって言ってた」
僕が答えると二人は目を丸くして顔を見合わせた。
「どうして待たなければならないのか、詳しく聞いてみたの?」
責めるようにテラが言った。
「ごめん、聞けなかった。今夜もう一度話をしてみるよ」
僕が言うとテラは目を潤ませながら頷いた。
「魚を獲ってくる」
誰にともなく言うと僕は海岸の岩場に向かって走り出した。テラの落胆する顔を見続けるのが辛かった。いつもの岩場だとテラが来るかもしれない。僕はいつもより遠くの海岸に足を延ばした。
その頃小屋ではソウがようやく起きてきて、テラ、ケンと三人で食事を取り始めていた。
「結局どうなったの?」ソウがケンに向かってたずねた。
「ラウトのお父さんはもう少し待てって言ったとさ」
ケンが答えると、ソウは天井を見上げ少し考えた後、再びケンを見て言った。
「ラウトが遭難した時も、ラウトのお父さんは舟に乗るなって言ったのだろう?とりあえず、言う通りにしておいた方が良いのではないの?」
突然テラが立ち上がると目頭を押さえながら扉を開けて外に出て行った。
「お姉ちゃん何だよ?」
椀を手にしたままソウがテラの背中に向かって叫んだが、テラはそのまま海岸に向かって走っていってしまった。
ケンはテラを追って立ち上がりかけたがふと立ち止まり、また座ると食事の続きを始めた。ソウが先ほど言った言葉が、ケンの頭の中で響き続けていたのだった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
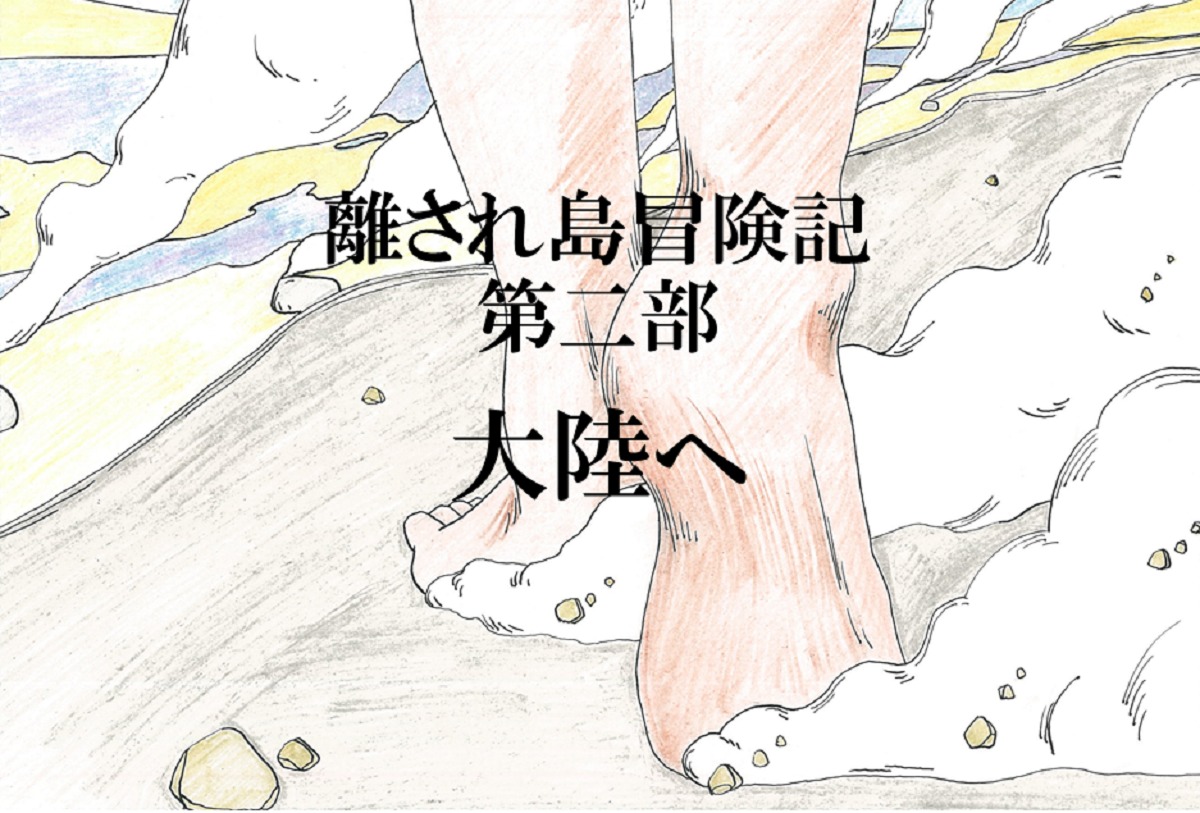


コメント