スポンサーリンク

その朝目覚めると、次々に形を変えながら凄い速さで動いている雲が目に入った。前の晩までは追い風と潮の流れに乗って順調に進んでいたはずの筏が、元来た方向に徐々に流されている。僕は立ち上がろうとしたものの、足元がおぼつかなくて立つことができなかった。いつの間にか波が高くなって、筏は前後左右に揺れていた。四つん這いになって周囲を見渡すと、ラウトが帆柱を支えにして立っていた。
「ラウト、この風は何だ?」
ラウトはしばらくの間、空をにらんでいた。そして、振り返ると言った。
「台風が来る」
「台風?」
僕は驚いてラウトに聞き返した。
「うん、台風は早いのと遅いのとがあるのだけれど、どうも僕らの後ろからゆっくり台風が近づいてきているようなのだ」
返事ができないでいる僕にラウトは逆に問いかけてきた。
「リョウ達の村でも夏になると度々大風が吹いていたと言っていたよね?」
「うん、夏から秋にかけて何度も大風が吹くのだ。山があるから風が巻いて、どちらから吹いてくるのかはわからないのだけれど、大風が一日吹いたかと思うと、ぴたっと止んで…」
肩に手が置かれたことに気が付いて僕は振り返った。ケンが緊張した顔で僕とラウトに目で挨拶をした。そして、僕に話の先を即した。ケンの後ろではテラが真剣な顔でこちらを見ている。
「その後、また逆の方から風が吹くのだよ。ただ、後の大風はそれほど強くないのだけれど」
僕は村で味わった大風を思い出しながら続きを話した。
「ラウトが言う台風も風が吹いたり止んだりするのかい?」
続いてケンがラウトにたずねた。
「うん、そうなのだ。強く吹いたかと思うと、何事も無かったかのようにピタッと風がやんで、しばらくするとまた風が吹く。渦巻きのような形をした雲が頭の上を過ぎていくのだよ」
ラウトが言う雲の形は僕らの村でも同じだった。
「そうだとすると、台風はラウトの島を通り過ぎた後、僕らの村の方に進んで行くということみたいだね」
僕は思いついた考えを話すと確認するようにリョウを見た。リョウもうなずいている。
「このまま北に、僕らの村の方向に進むということは、台風に追いかけられるということになるね」
ケンがラウトに言うとラウトもうなずいた。ラウトとリョウは黙ってしばらく考えていた。そして二人同時に声を上げた。
「リョウ、西に向かおう。台風を避けるにはそれしかない」
意外な話に僕は問い返した。
「島のある東に行く方が良くないかな?」
「台風は島の近くを通ることが多いのだ。今のままなら島に着く頃に最も海が荒れるだろう。岩場に叩きつけられたらひとたまりもない」
ラウトの言葉に僕はうなずいた。
「わかった。いずれにせよ、このまま北に向かうのは危険だ。二人が西というなら西にしよう」
納得して僕は言った。
「ちょっと待って。村とは違う方に行くのはいやよ」
テラが後ろから大きな声を出した。
僕とケン、ラウトは揃ってテラの方を見た。これほど、悲しそうなテラを見るのは初めてだった。彼女の気持ちは痛いほどわかった。でも今は生き抜くことが最も大事なのだ。僕はテラの近くまで這っていき、彼女の肩に手をかけて言った。
「テラ、台風さえやり過ごしたらまた北に向かうから大丈夫だよ。嵐に巻き込まれたらどのくらい大変なことになるか、僕らはよく知っているではないか」
長い間、彼女は僕の目を見ていた。そして顔を背けると小さな声で言った。
「わかった」
「必ず村に行くよ。約束する」
テラにそう言うと僕は帆柱まで行って、筏が西に進むようにラウトと共に帆の向きを変えた。そして流れる雲をもう一度見上げた。
「うーん、お腹いっぱいだよ」
後ろからソウの寝言が聞こえてきて、僕らは目を合わせて思わず笑みをこぼした。
「安全な場所に着くのは夜になるかもしれない」
ラウトの言葉に、僕らは代りばんこで休みながら筏を西に進めることにした。西とはつまり大きな陸地に行くということだ。ラウトが言うには、大きな河が海に注ぎ込むところが最も近く、桟橋という木で組まれ海に突き出た橋があって、筏を繋ぐのに最適だということだった。話はそもそも橋とは何かというところから始まった。そういう話に食いつくのはもちろんケンだ。ケンは幾度もラウトに質問をして、一旦話を飲み込むと今度は僕らにかみ砕いて説明してくれた。暗くなる頃、僕らは大きな陸地についておおよその事を理解していた。そこには王という立場の人がいて、人々は王の元で暮らしているというのだ。王は北や南から攻めてくる敵と戦い人々を守ることで尊敬を集め、代わりに人々は王の望むように食べ物を納める。人々の中には兵士となり、王と共に戦う者もいるという。敵がいない時の兵士は、王の命令で道はもちろん桟橋を造ったりもするということだった。島を出る時に集めた貝殻は、王やその家族が人々の前を行進する時に身に付ける物として、兵士が集めているらしい。ラウトの口から次々に出てくる言葉は僕らにとって途方もない話だった。
話がとても興味深いため、僕らは台風に対する恐怖よりも彼の話に夢中になった。そうこうしている内に、雲の切れ間が朱色に染まり僕らの向かう方向に日が沈んでいった。あっという間に周囲は暗くなった。しばらく海の向こうを眺めていたラウトがふいに指さして言った。
「見て!明かりだ!」
小さな光がちらちらと瞬いているのが目に入った。驚くほど大きな河口が僕らの前に現れた。その後ろには薄ぼんやりと陸地らしき影が浮かび上がっている。ラウト、ケン、僕、テラ、そしてソウの四人は筏の端から茫然としてその景色を眺めていた。そして陸地が近づくにつれ、僕らは自然と手を繋ぐのだった。初めて見る大陸が僕らを圧倒するように眼前に広がっていた。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
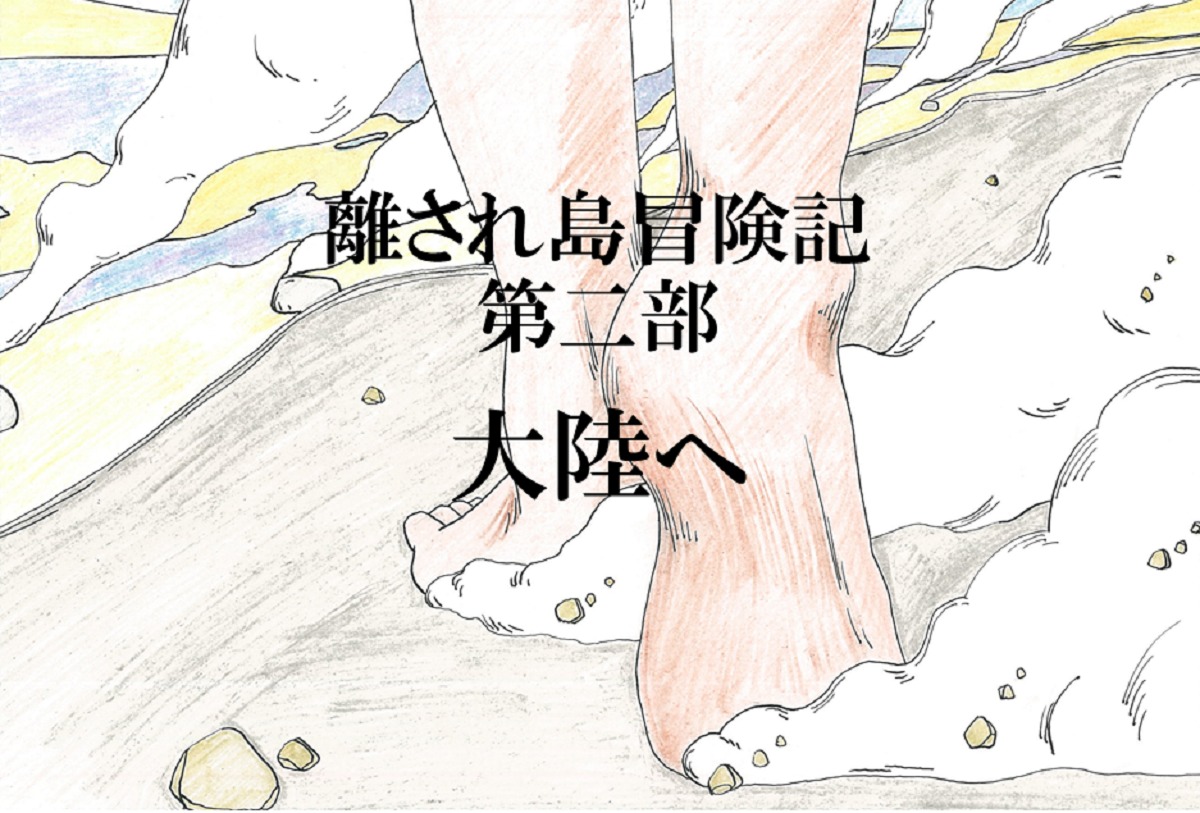


コメント