スポンサーリンク

翌朝から僕らは朝日が昇ると共に叩き起こされて、鉄作りに駆り出されることとなった。実のところ、叩き起こされたのも駆り出されていると感じていたのもソウだけだった。僕とケンは鉄作りを学ぶ機会が巡ってきたことに興奮していた。そして出来ることなら剣を作れるようになりたいと密かに考えていた。最初の数日こそ、様子を見る為に指示されたことだけをしていた。そうしながらも簡単な言葉だけでも憶えようと、僕らはここで働く人達の話に耳をそばだてた。もともと海の上での暇つぶしに大陸で使う言葉のいくつかをラウトに習っていたおかげで、ごく簡単な言葉を知っていたのが役に立った。いや、それ以前にラウトとも違う、別の言葉を使うという事を予め知っていたからこそ、たいして戸惑うことなくここでの生活に馴染むことができたのだ。離され島でラウトの使う言葉を話せるようになった経験から、僕らは他所の言葉を憶えるコツのようなものを身に付けていた。最初に相手が発した言葉を聞こえた通りに言い返す。正しく言えれば相手はうなずくし、そうでなければ首をかしげてもう一度言う。人とはそういうものなのだ。その次は、相手が何を言いたいのかを想像して行動してみる。正しく行えていれば相手は満足する。そうでなければ、その相手は自ら手本を示そうとする。そこで言葉と行動が僕らの中で結びつくのだ。僕らは次第に言葉と仕事の両方を身に付けて行った。そして人手が必要とされている仕事とみるや積極的に参加の名乗りを上げるようになっていったのだった。そこにはかつて僕とケンで語り合った旅をしなくて済む方法が、ここでの生活を通して見つかるという確信めいたものがあったからだった。
朝と夜、テラが僕らのいる所に顔を出した。彼女はここで働く人達に食べ物を配る役目を与えられたのだった。驚いたことにテラはここの言葉を僕ら以上に早く身に付けてしまったのだ。彼女が言うには、テラより少し年下の女の子二人と仲良くなって、その子達とやり取りするうちに自然と憶えてしまったという。僕とケンはその話を聞いて顔を見合わせた。そう言えば、仕事中はともかく寝泊まりする建物の中では二人で話し込むばかりで、他の人達と話す機会をもてていなかった。仕事が終わって帰ってくると、テラが食事を運んでくる。器に食べ物が注がれる間に、お互いの状況を確認し合う。テラが行ってしまうと、ソウ、ケン、そして僕で夕食をとりながらその日に起こったことを話し合うのだ。食事が済むと、ソウはぷらっとどこかに出かけて行く。どうもテラのいる厨房という所、つまり食べ物を作る場所に出入りしているらしい。二人になった後もケンと僕はあーでもないこうでもないと、鉄作りの手順を付け合わせていたのだった。それはそれで意味のあることだ。だが僕らが知りたいことのほとんどは、ここの人達と話せるようになることで自然と得られるのではないか。テラの話を聞いてそう思い至ったのだった。以来、僕は大まかな話をケンと済ませた後は、建物内をぶらつくようになった。そして仕事で知り合った長を見つけては声をかけた。そのようにして顔を憶えてもらうことで、現場で声をかけられることも多くなった。僕は望み通り、色々な仕事に関われるようになっていった。仕事以外での人とのやり取りが苦手なケンは、そんな僕を遠めに眺めながら一人でいることが多くなった。そんな僕らの様子をソウから聞いたらしく、テラが心配して声をかけてきた。傍から見ると、ケンが孤立しているように見えるらしい。実のところそうではなかった。僕が知り合いを増やし、鉄作りの手順についての話を広く集めてくる。それを一切漏らさずケンに伝える。僕から聞いた話について、ケンは一人考え続ける。静かに、様々な物事がケンの中で深く掘り下げられて結び付いていく。そうして繋ぎ合わさった知識と想像、そして疑問が、また僕のところに返ってくるのだった。毎朝毎晩、繰り返されるこのやりとりの中で、いつしかケンの鉄作りについての知識は、一切を一人で為しうるのではないかと思えるほど高い位置に達していた。
食後ぶらつく間に、僕は新たな楽しみに出会うことになった。それは薄い板に書かれた升目の交点に白と黒の石を一手ずつ交互に置き合う遊戯で、通称「白黒」と呼ばれるものだった。これは片方が白石を持ちもう片方が黒石を持つ、二人でやる遊びだった。沢山ある升目の交点を陣地と見立てて、なるべく広い陣地を得るべく互いに代わるがわる石を置いて囲い合うのだ。最終的には陣地の広い狭いを競い合うものなのだけれど、相手の石を完全に囲うと相手の石を升目から取り上げることもできて、なかなか白熱する遊戯なのだった。だれかが白黒を始めると、周囲には人だかりができる。皆、勝負している二人の一手毎に歓声をあげ、また下手な手を打つと落胆して罵声が飛ぶのだった。最初は興味本位に覗き込んでいただけだったものの、知り合いの長に声をかけられて僕も遊ぶようになった。単なる石遊びと思っていたがそうではなかった。相手の石を取って勝ったと喜んでいると、実は陣地の広さで負けていたりと、思った以上に奥が深いのだ。僕は白黒にのめり込み、いつの日か白黒やりたさにぶらつくようになっていった。
「白黒つけるか」
「白黒つけよう」
そうして始める勝負のなんと面白いことか。この白黒を通して、僕はいくつかのことを新たに知るのだった。最も大事なことの一つは数。陣地の広さを競う上で、自分が手にした升目の交点を数える必要が白黒にはあるのだ。そしてもう一つは、ある男との出会いだった。誰よりも白黒にたけて負け知らず、それがクレと呼ばれる男だった。
いくつかの勝負が終わって、場が和んだ頃、クレは突然現れる。クレは常に数人の兵を従えていた。そして周囲を見渡すとこういうのだった。
「最も強い奴はどいつだ」
勝ち数の多い人がおずおずと手を挙げる。するとクレは言い放つ。
「おまえ、白黒つけるぞ」
この勝負を断ることは誰にもできなかった。断れば兵によって酷い目に遇わされる。クレはこの鉄炉の主なのだった。クレはどんな時でも腰に剣を下げて現れた。そして、その剣を鞘から出して升目の横に置く。切先を向けられた相手は、それだけで怯んでしまうのだった。そうしてクレは言う。
「俺に勝ったらこの剣をやる。だが、無様に負けるようだったらこの剣でお前の首をはねてやるからな」
だらだらと汗を流しながら勝負に挑む相手をよそに、クレの表情は常に余裕だった。そして、どの相手にも余裕で勝ってしまうのだった。勝負が済むと、クレは剣を相手の眼前で一振りして鞘にしまう。その所作に相手が失神してしまうことすらあった。実際にはクレに首を切られた者はいなかった。何故なら一人減ればその分鉄作りが大変になるからだ。とは言え、毎晩行われるこの振る舞いによって、鉄炉におけるクレの立場は強固だった。そんなクレの立ち居振る舞いの全てに目が離せなくなった自分に、いつしか僕は気が付いていた。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
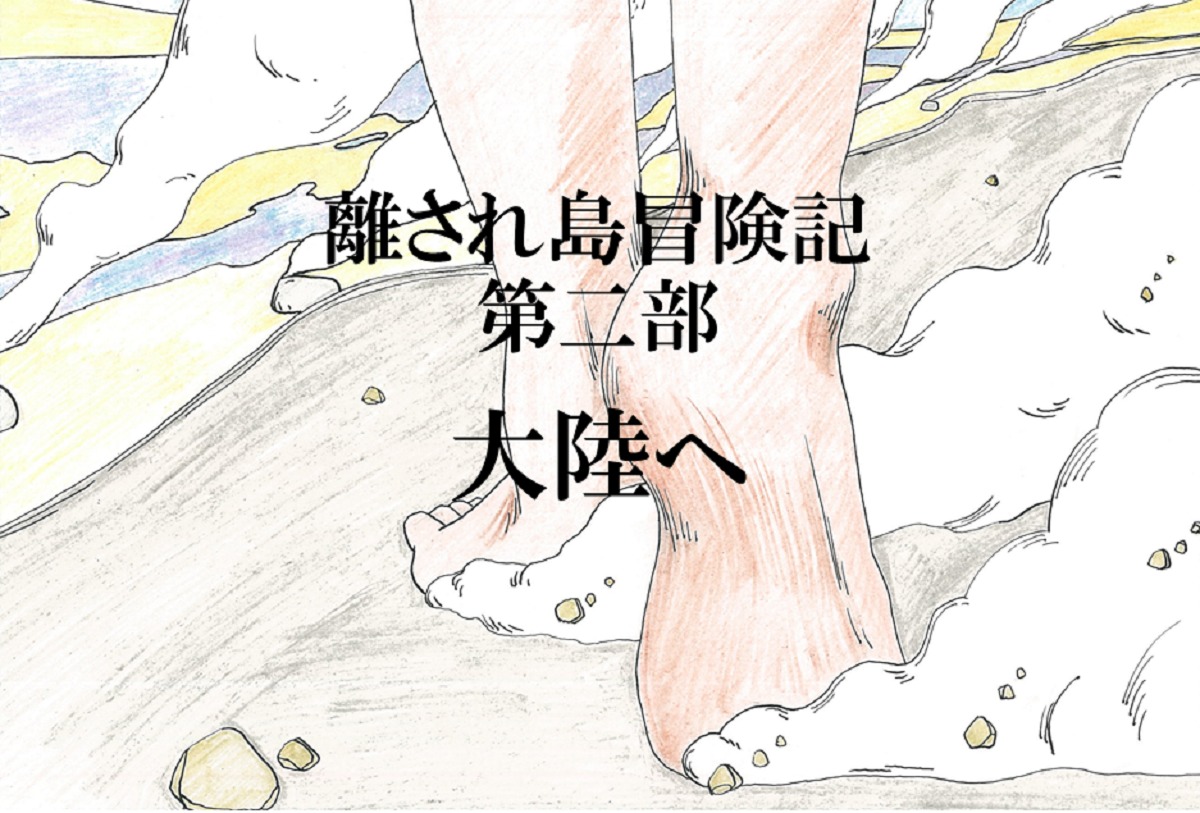

コメント