スポンサーリンク

海と河口の境目で夜を明かすことになった。老人から子供まで、みすぼらしい恰好をした人達が集められた所に僕らも加わることになった。女性も何人かいる。取り乱していたテラも今は落ち着いて、ソウと肩を寄せ合って目を瞑っている。眠れる時は眠っておいた方が良い。ケンも目を閉じているものの、何かを考えている様子だった。僕はこれから起こることをつぶさに見ておこうと、度々薄眼を開けて周囲を見渡していた。海が徐々に明るくなっていく。そして朱色の太陽が頭を出すのと同時に、河上から大きな船が近づいて来るのが目に入った。左右に櫂の漕ぎ手が配置されていて、屋根までついている。その船が桟橋に到着すると、兵隊はそこにいた全員に船に乗るように即した。僕らはただ従うしかなかった。舟に乗ると船底には腰かけられる出張りが並んでいて、テラ、ソウ、ケン、そして僕はちょうどうまく並んで座ることができた。船底とは言え、多少は周りを見渡せる薄い形の船だった。僕らを連れてきた兵の内、何人かが一緒に乗り込んで来た。そして船の長らしき人にお金を渡すと何かをささやいた。船長は顔を上げると櫂の漕ぎ手に向かって声をあげた。
「てつろへ向けて出発!」
その言葉と同時に桟橋に縛り付けられていた縄が外されて、ゆっくりと船が進み始めた。行先が決まったようだ。目の前の大河を船は登り始めた。既に完全に顔を出した太陽の光を浴びて、河は黄金色に輝いていた。水面に揺らめく光の道を目にして、不安よりも何かに期待している自分の気持ちを僕は抑えることができなかった。
しばらくすると、温かい汁が入った器が皆に配られた。中身は昨夜屋台で食べたものと似ていたが、薄茶色の粒々はごくわずかしか入っていなかった。がっかりしながらもゆっくり飲み干すと、それでも気持ちが和むのがわかった。隣に座っていたケンが肘でつついてきた。
「殺されるわけではなさそうだ。良かったな、リョウ」
ケンの言葉に僕はうなずいた。
「そのようだ。殺すつもりなら何も食べ物を与える必要はないものな」
小声で返事をしたつもりだったものの、近くにいた兵が聞きつけて剣を突き付けてきた。慌てて僕らは下を向いた。それを機に、船上で聞こえていたひそひそ話は一斉に止んだ。兵達は、一同の中で唯一言葉の通じない僕らに注意を向けているようだった。
「他の船をよく見ろ!」
午後遅くなって、うつらうつらしているところに船長の声が響いた。目的地が近づいたようだ。周囲にいくつもの船がひしめいている。桟橋に船をつけるべく、それぞれが順番待ちをしているのがわかる。しばらくして僕らの乗る船の番が来た。兵達の指示で立ち上がった途端に周囲の景色が完全に目に入った。木も草も無い、平らな黄色い大地が眼前に広がっていた。朝方の海の香りから一転して、ここでは何かが燃えているような匂いが感じられた。改めて見回すと、僕らの乗った船のように人を運ぶ船ばかりでなく、赤茶色や白い土を積んだ船が周囲を取り囲んでいた。
桟橋に降り立つと、一緒に乗っていた兵達は僕らを挟むように前後にわかれた。そして最後列の兵は、前の兵について行くように僕らを追い立てた。皆、仕方なく兵の言う通りに歩き出した。その時、ケンがまた肘で僕を突いた。ケンの視線の先を見ると、むしろで覆った荷物を載せた車が横を通り過ぎていく。重そうな荷物の端がむしろからはみ出ていた。それは沢山の剣だった。僕は背中がぞくぞくするのを感じた。度々振り返って見ていると僕らが乗っていた船に積み込まれるようだ。どこかに運ばれていくのだろうか。
「リョウ、こんなことを言ったらテラに怒られると思うのだけれど、僕は少しわくわくしているのだ」
小声で話しかけるケンの口元に、微かに笑みが浮かんでいるのがわかった。
「ケン、実のところ僕もそうなのさ」
僕の返事に、ケンは素早く周囲に視線を送りながらこう言った。
「これから起こることは全て残らず憶えておく必要がありそうだ。リョウも頼んだよ」
後ろにいた兵がケンと僕の背中を小突いた。それ以上話すなということなのだろう。僕は横目でケンを見て小さくうなずいた。
「姉ちゃん!」
ふいに、ソウの声がした。
前を見ると女性だけが別の所に連れて行かれるようだ。
「テラ!」
僕は驚いて大きな声でテラを呼んだ。途端に後ろから兵に蹴り飛ばされてしまった。倒れたところを更に背中を踏みつけられて、僕はうめいた。テラは振り返ると這いつくばっている僕に向かって静かに首を振った。そして、そのまま兵に連れられてどこかに行ってしまった。テラはどうなってしまうのか。僕は何もできない自分に歯がゆかった。
兵に即されて立ち上がった後、ソウ、ケン、そして僕は歩き続けた。河岸には僕の背丈より少し高いくらいの大きな筒が何か所かあり、それぞれ炎らしきものが立ち昇っていた。他に炭を焼いている小屋もいくつかあった。壁から突き出ている筒から白い煙が沢山吐き出されていることで炭だとわかったのだ。それぞれの場所で男達が働いている。兵は所々で止まっては長と思しき人に声をかけた。そして何か相談したかと思うと集団の中から何人かをその長に渡すのだった。最初に別れたのはケンだった。
「これからやることは何であれ、できるだけ憶えておいてくれ」
別れ際にケンはソウに言った。ソウは黙ってうなずいた。やがてソウとも離ればなれになって、僕は孤独になった。結局、僕は最初に着いた桟橋に戻ることになった。
僕を引き受けた長は桟橋に着いた船から荷を降ろすように身振り手振りで指示を出した。僕は何人かの男達と力を合わせて荷を降ろすと、用意された車に乗せた。荷は大量の赤茶けた石の塊だった。船上から見た赤茶色の土はギザギザした石が沢山集められた物だったのだ。僕は後ろから車を押す役となった。長の指示に従って進んで行くと、大きな筒のところで車は止まった。粘土で作られた筒の天辺からは、先ほど同様炎がめらめらと立ち昇っている。筒の中でよほど多くの物が燃えているのか、近くまで来るとかなりの暑さだった。筒の横には櫓が建てられていて、上には男がいた。時折炉の中に赤茶けた石をざーっと投げこんだり、重そうな棒でかき回したりしている。下で待機している別の男に運んできた物を渡すと、僕らは荷が空になった別の車を与えられて桟橋に戻ることになった。
結局、夜遅くまでその繰り返しだった。代わりの男達が現れて解放される頃には、僕は疲れてくたくたになっていた。とは言え、一緒に働いたことで幾人かの男達とは気心が知れるようになった。彼らに連れられて、僕は大きな建物に入って行くことになった。そこでは食事が出る上に眠る場所もあるようなのだ。中に入るとソウとケンが話しているのが見えた。僕はほっとして二人に駆け寄った。二人ともついさっきまで働いていたとのことだった。ソウは小屋から炭を取り出し炉に運ぶ役、ケンは火の消えた筒の底から引き出されたごみを捨てに行く役目だったらしい。ソウは疲れ切っていたものの、ケンの目はきらきらと輝いていた。
「ほら食べなよ!さっき姉ちゃんが食事を運んできてくれたのだ。どうも炊事場を手伝うことになったらしい」
ソウの言葉に僕は胸を撫で下ろした。ソウから器を受け取って僕は食べ始めた。船の中で食べたのと同じ汁だったものの、薄茶色の粒が沢山入っている。魚の切り身も入っていて美味しい。僕は疲れが一気に霧散していくのを感じた。
「その粒は米というらしいよ」
ソウが教えてくれた。米の歯ごたえを感じながら、僕はこの先のことを考えた。ここには少なくとも食べ物と寝る場所があり、仲間もいる。何があっても皆が一緒にいれば何とかなる。その上、これまでと違う何かを知ることさえできそうなのだ。
「これは好機だ」
「何言っているの?大変なことになっているのだぞ」
何気なく発した言葉にソウが口を尖らせた。だがそのすぐ後ろでケンが、僕の思いに同意してうなずくのが見えた。
「親分、奴らは鉄炉に連れて行かれたようですぜ」
ガリの報告にリキは首をひねった。
「鉄炉まではかなりあるぞ。確かなのだろうな?」
「もちろんですよ。奴らを乗せていった船が戻って来たので、船長に礼をはずんで訊いたのでさ」
ガリが自信ありげに首を縦に振った。そして、立て替えた金を求めて手を差し出してきた。リキは舌打ちをして胸元から袋を取り出すと、中から幾ばくかの金を取り出してガリに渡した。ガリは満面の笑みを返した。
「どうする?本当に助けに行くのか?」
リキは後ろを振り返って言った。その先のラウトの眼差しに迷いはなかった。
「新しい剣も手に入れたいしな。よし、やってみるか」
リキはすくっと立ち上がった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
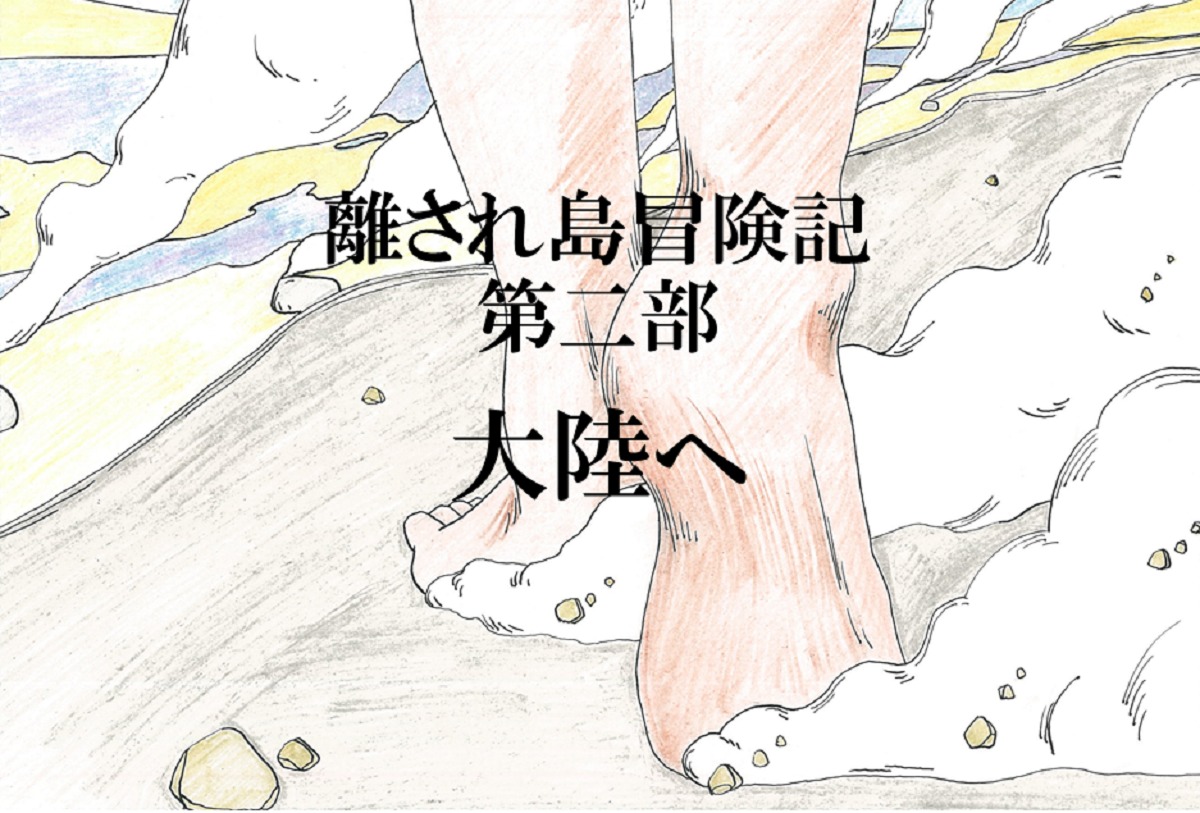


コメント