スポンサーリンク

最初に目に入ったのは、細長く伸びた背の低い炉とその手前に座っている一人の男だった。男の右手にはこてが握られており、そのこては、鉄の塊を挟んでいた。鉄塊は今、炉で熱せられている。男の左手は炉に風を送るふいごの取手を握っていて、ゆるやかに前後していた。炉からはごーという音と共に黄色い炎がめらめらと立ち昇り、火の粉が舞い散っていた。座っている男の右側には四角い台があり、その更に右には二人の男が槌を構えて立っていた。座っている男がうなずいたかと思うと、炉に差し込まれていた鉄塊が取り出され、素早く台の上に置かれた。鉄塊は眩い光を放っていた。途端に二人の男が、鉄塊目掛けて槌を振るいだした。座っていた男はこてを左手に持ち替え、空いた右手で自らも槌を振るいだした。三つの槌が奏でる音は、まるで音楽のように小気味よく響き渡った。明るい橙色に輝く鉄塊は、火花を上げ、徐々に長く伸び始めた。初めてみる光景だ。僕らは普段、鉄をドロドロに溶かして型に流し込む。槌で打って形を整えるなど、考えもしない作業だった。男達の手前左手にある鉄炉が目に入った。普段作業しているものに比べて小さな炉だった。そこにも男が付き、ふいごで風を送っていた。くべられた炭にはまんべんなく火が行き渡り、黄色い炎がちらちらと上がっていた。そして鉄炉の左側には鉄鉱石置き場、鉄炉の右横には、出来上がった鉄塊置き場があるのがわかった。こぶしで握れる程度の鉄塊がいくつも並んでいる。目の端々で場の状況を捉えながらも、僕は鉄鉱石置き場に向かって荷車を押した。すぐ後ろをケンがついて来るのがわかった。不思議なことにこれだけ見ている間に進んだ歩みは、急いでいるにも関わらずわずかに二歩、三歩といったところだろうか。僕には今、目の前で行われていること全てがゆっくりと感じられているのだった。
鉄鉱石置き場に足を進めながらも、僕は三人の男から目を離すことができなかった。座っている男は槌から手を放すと板状になった鉄の取手を持ち、鉄塊の真ん中辺りに直角に据えた。残る二人がその鉄の板に槌を打ち下ろす、平たく伸びた鉄塊の真ん中が見る間に筋状に凹んでいく。半分に切り分けるつもりなのか。目の前で起きていることの全てが、僕には理解しがたいものだった。
「いつもの奴ではないな。お前ら何者だ?」
ふいに背後から声がした。監視役の兵だった。
「いえ、運んでいた人が足を痛めたようなので代わりに…」
僕は慌てて歩みを止めると、振り向きざまにそう返事をした。
「すぐに出ていけ!」
その兵は明らかに怒っていた。その手は腰に下げた剣の柄にかかっている。
「はい」
僕とケンは鉄鉱石が載せられた荷車をその場に置くと、一目散に出口に向かって駆け出した。振り返る余裕は無かった。土壁までが恐ろしく遠く感じられた。僕らは土壁に開いた扉を潜り抜けて外に飛び出した。土壁の外には相変わらず炭焼き小屋から出る煙が漂っていたが、なぜかいつもより明るく感じられた。大きく息を吸った後、最初に目に留まったのはリキの顔だった。口角が微かに持ち上がるのがわかった。
「見たか?」
声の無い声が聞こえたような気がした。僕とケンは同時に首を縦に振った。笑みを残し、納得したように背中を向けようとしたリキ。その左肩がぴくりと動き、こちらに向き直った。いやな予感がした。
「待て」
後ろから声がした。土壁の中にいた兵とは違い、その声は落ち着いたものだった。振り返ると、そこにはクレがいた。声の感じとは裏腹にクレの目は冷たく燃えていた。その右手には、既に鞘から抜かれた剣が握られていた。
別バージョン
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
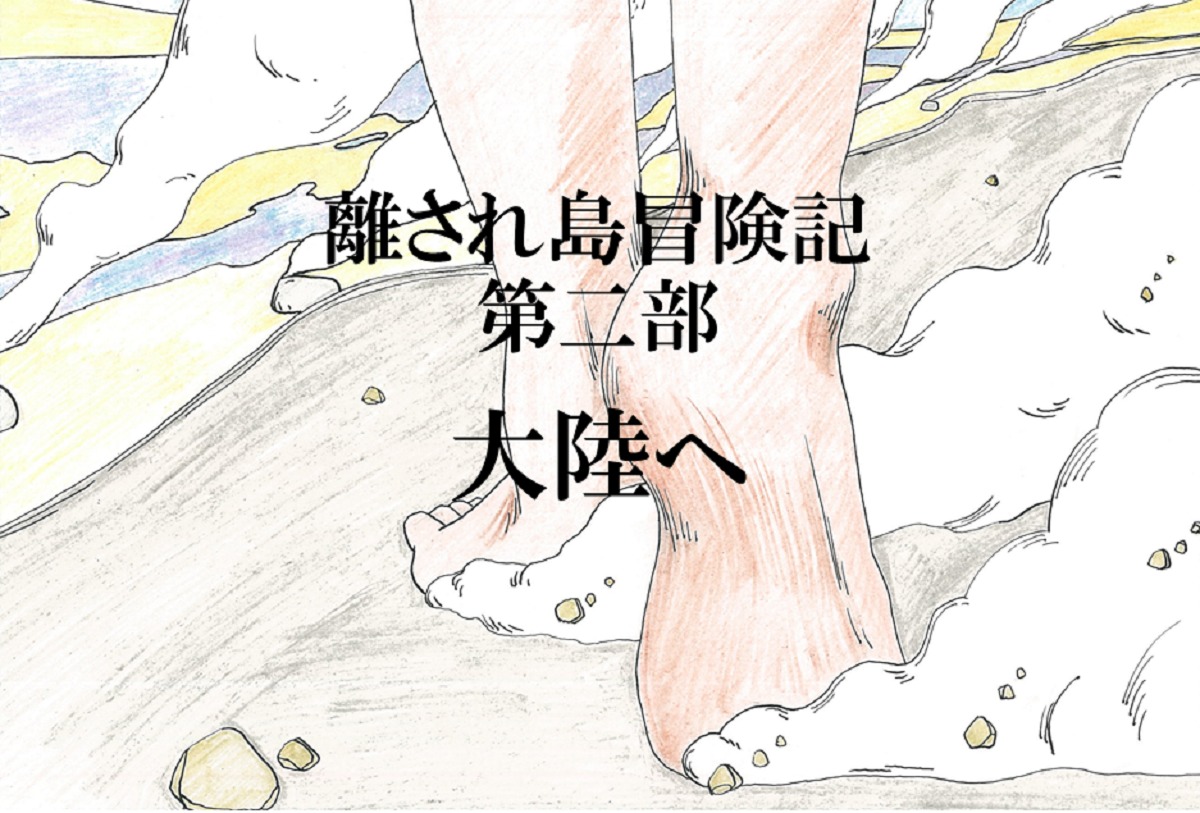

コメント