スポンサーリンク

この川をたどれば故郷の村に行き着くことができる。少しでも早く村について、母さんや父さん、そして、長く離れている友人達に会いたい。そんな思いを胸に抱きながら、僕達は木の根を跨ぎ、春から夏に向かう季節の中で鋭く切れやすい葉を伸ばしつつある草を掻き分けながら進んだ。逸る気持ちとは逆に、一日に歩ける距離はごく限られていた。山道を歩き慣れていないコウとサイ、ラウトが足を引張ることもある。だが、長い海の上での生活で櫂を漕ぐ腕が太くなったのとは逆に、僕ら自身がとても山育ちとは思えないほどほっそりとした足となってしまっていた。もどかしい。一歩進む度に、思い通りに動かない足に怒りが湧いてきた。ただ一人、ソウだけは山道にもめげることなく歩けていた。陸地に着く度にあちらこちらへと走り回るソウのことを「無駄に走る」と揶揄していた僕らであったが、こうなってみると、好奇心から走り回らずにいられないソウの行動が、実のところ理にかなったものだと理解できるのだった。一番元気に動き回れるソウが、先頭に立って地を固め草を払って道を作ってくれる。後に続く者からすれば、これほど有難いことはない。旅の途中で、ソウの行動に姉としてあれこれ文句をつけていたテラも、ここに至ってソウの存在を認めざるを得なくなったようだ。ソウを注意するテラの声が木の葉を揺らすことはめっきり少なくなり、むしろ、ソウの後ろ姿を頼もし気に見つめることの方が多くなっていたのだった。日々、進まない行程に心折れそうになりながらも、周囲を囲む木々は海に近い頃の黒松や楠から、ブナ、ミズナラ、朴木を多く含むものに変わっていった。木立を渡る風の匂いに変化を感じながら、少しずつ故郷の山に近づいていることを僕らは肌で知るのだった。
幅の広い川幅が徐々に狭くなり、穏やかだった水の流れも、今や轟々と音を立てて岩を縫うように走っている。その日、山肌に夜露を凌げる窪みを見つけて、僕らは野営の準備に入った。野営に適した場所はそうそうあるものではない。見つけた時は、それが昼頃であろうが何であろうが、そこにすると決める必要がある。太陽は傾くことなく真上に位置していている。もう少し進みたい気持ちを抑えて、七人は荷物を解いた。僕とケンは早速魚を獲るために岩場に降り、ソウは獣を狩るべく弓を持って駆けていった。テラは、皆の荷物の中から洗い物を取り出すと、川で汚れを落とし始める。ラウトとコウ等二人の姉妹は、疲れ切っており、川に突き出した岩に腰かけて足を水に浸している。川の両側は大きな岩が所々見え隠れする切り立った崖となっていた。時折聞こえる鳥の声と、飛んでいるアブの音が、間もなく夏が訪れると囁いている。
「リョウ、今日は魚がいないね」
並んで釣り糸を垂れているケンが言った。
「うん、こういう日もあるのだな」
ほんの一、二匹しか釣れていないヤマメを目の端に捉えながら、僕は独り言のようにつぶやいた。
「ソウが何か獲って来てくれるとよいのだけれど」
ケンの言葉に少し不安覚えながら、僕は水面に魚影を探し続けた。
スポンサーリンク
ソウが息を切らして戻って来た。
「山の方で雨が降ってるよ」
川の上流を指差しながらソウは言った。
「え?」
と言って、僕とケンはソウが示す方を見つめた。青空だったはずが、頭上を雲が取り巻きつつあることにようやくその時気が付いた。僕らが進もうとしている先の空は、既に真黒な雲に覆われている。その時、肩に雨の最初の一粒が当たった。空を見上げると、僕らの上も黒い雲が流れてきていて、その量はどんどん増えていた。僕らが立っている岩の色を雨が染め出した。野営場所の都合上、両岸を切り立った壁に囲まれた川幅の極めて狭い場所に僕らはいた。やらなければならない事はただ一つだった。
「皆、今すぐ荷物をまとめてくれ!」
僕は大声で叫んだ。てんでばらばらに皆が動き出した。まとまった荷物から順にラウトが山肌の窪みに運び始めた。
「ラウト、そこではない。もっと上だ」
「え?でも濡れずに済むのはここしかないよ」
真剣な目で言う僕にラウトが意外そうな顔をして言った。
「濡れるのは仕方がない。出来るだけ上に登るのだ。濡れるよりもっと大変な事態になる前に」
僕らを見下ろすように張り出した岩場を見上げるようにして僕は言った。
「上?とにかく上に行くんだね。わかったよ」
ラウトは一旦置いた荷物を改めて背負うと、コウやサイの荷物を持って先に崖を登り始めたソウに続いた。ラウトの後ろをコウとサイが時々足を滑らせながら登っていく。僕はまだ下に残っているテラの所に走った。他の女の子に比べて多くの荷物を抱えるテラは、ようやく荷物をまとめ終わった様子だった。
「テラ、荷物は僕が持つ。早くソウに続くのだ」
「リョウ、わかったわ」
テラは一瞬だけ僕の目の奥を覗いた後、頷いた。
「ケン、急ごう」
「よし」
雨は既に大振りとなっていた。最後になった僕とケンは、濡れて滑りやすくなった崖をようやく登り始めた。岩のすき間を雨水が流れ始めていて、登りやすい道筋は限られている。ケンを先に行かせてその後に僕は続いた。野営をしようと考えていた窪みの、天井となる大岩の上にたどり着いた時だった。川上の方からごおっという音が聞こえ始めたのだ。
「来たぞ」
「うん」
ケンと僕は息つくことなく更に登って行った。
「来るよ、来る。リョウ、ケン急いで!」
上からソウが声を掛けてくる。見上げると心配そうに見下ろす皆の顔が見えた。彼らが立つ場所は大きな岩ががっちり噛み合っていて丈夫そうだ。その時、ほっとした僕の耳に大きな音が響いた。その方向に顔を向けると、これまで見たことも無いような激しい濁流が上流からやって来るのが目に入った。転がる岩。水に土を流されて倒れた巨木が水を堰き止める。行先を失った水がしぶきを上げて僕らを襲ってくるようだ。先ほどまで綺麗な水の流れだった川が、今や薄茶色に濁り、うねり、まるで生き物のように蠢いている。川の中ほどにあった大きな岩も軽々と運ばれて、下流に押し出されていく。あまりの勢いに僕の足は恐怖ですくみ、それ以上動けなくなった。
「リョウ、あと少しだ」
ケンの声で我に返り、僕は改めて少しずつ足を進めた。ようやく上までたどり着いた僕達をソウとラウトが腕を取って引き揚げてくれた。雨の中ですら寒さを感じないほど、恐怖が興奮となって身体の中を駆け巡っているのがわかった。その後、僕らは長く蠢き続ける濁流を呆然と眺め続けるのだった。
青空が戻った。倒れずに生き残った木の葉っぱから澄んだ水が滴っている。夕暮が近づく中、僕らはなんとか山壁を降りて、最初にいた辺りに辿り着いた。野営しようとしていた窪みは周囲の岩や土を全て流されて、見る影も無かった。全てが濡れていて、薪にできそうな木などは有りそうもなかった。皆で寄り添って暖を取るしかないかと暗澹たる気分に陥っていたその時だった。
「リョウ、これ見てごらん」
ケンが足元の石を取り上げて僕の方に差し出した。見ると、それは紛れもなく鉄を含んだ石だった。
「ケン、これは」
「うん、鉄だ」
僕の言葉にケンは確信したように頷いた。妙に黒っぽく見える水溜りに手を差し入れて、そこに溜まった砂をすくってみる。
「砂鉄だ」
「さっきの濁流で、表面の土が洗われたのだね」
「うん、上流から流されてきた土の中で、重い鉄だけが岩のすき間に残ったことも考えられる」
ケンの話を耳にしながら、僕はリキと別れた時のことに思いを馳せていた。
「鉄は龍と共にある」
そして、もう一つ。
「天の龍、地の龍」
彼はそう言っていたのだった。
「わかったよ」
全てを押し流すように蠢いていた濁流を思い出しながら、僕はケンに向かって言った。居たのだ、地の龍が。ついさっきまでここに。この場所に。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
前話に戻る
1話に戻る
第二部1話に戻る
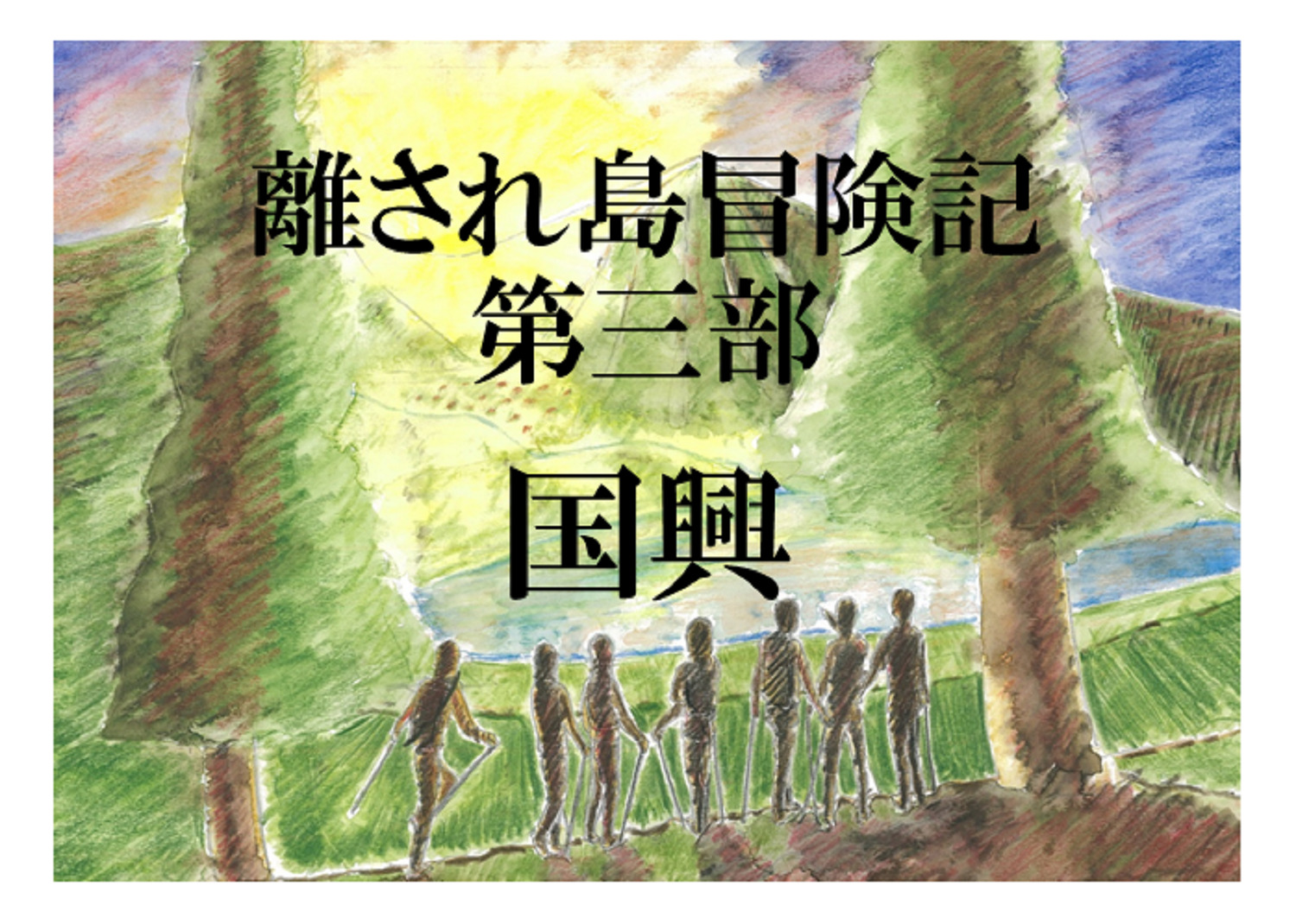

コメント