スポンサーリンク

初めて食べる薄茶色の粒々した物はそれ自体には味がないものの、汁の味を邪魔することなく空腹を満たしてくれた。海の上で魚ばかり食べていた僕らにとって、久しぶりのご馳走だった。皆は差し出された温かい食べ物をあっという間に食べ終えてしまった。海風で冷えていた身体がほかほかして気持ちが良い。ソウはお礼を言おうと先ほどの食べ物をくれた人に声をかけた。しかし、その背中は凍ったように固まった。
「金、金!」
相手が右手を差し出してお金というものを要求してきたのが、ソウの背中越しに僕らにも伝わってきた。僕とケン、そしてテラは慌ててソウの元に駆け寄った。
「さあ金を払え!」
大きな身体をした相手は、僕らを見下してにやにやしながら言った。ラウトに言葉を習っていたおかげでその程度は理解できた。そもそも食べろと言ったのは相手の方なのだ。だが、どう言い返して良いのかがわからない。
「食い逃げだ!」
奥から屋台の主人らしき人が出てきたと思うと、大きな声で叫んだ。それまで周りにいた人々が巻き添えをくうまいと僕らから急いで離れて行った。周りを見物人に囲まれて、僕らは逃げることすらできなかった。突然、沢山の強そうな男達が現れて僕らの周りを囲んだ。皆が手に剣を持っている。先ほど王の兵隊が持っていた青銅の物ではなく、良く切れそうな鉄で造られた剣だった。多少身軽そうではあるものの、男達の恰好は王と共に行進していた兵隊達とよく似ていた。彼らは僕らに向かって何かを言った。だが、初めて耳にする言葉で意味がわからない。
「あ!」
テラが何か思いついたのか胸元を探った。そして屋台の主人の元に駆け寄ると星屑石で作った刃物を差し出した。その男はテラの手から星屑石をつまみ上げると不思議そうに眺めまわした。が、ふんっと鼻を鳴らしたかと思うと星屑石を足元に落し、テラの胸を腕で突いた。
「うっ」
テラが胸を押さえてかがんだ。
「姉ちゃんに何をする!」
ソウが叫んだ。すると、すぐ脇にいた兵の一人がソウの顔を平手で思い切りはたいた。ソウは吹飛んで倒れこんだ。
「ソウ!」
顔を上げたテラが駆け寄ろうとするも、兵にがっちり腕をつかまれて引き止められてしまった。隣にいた兵が剣を抜いたかと思うと僕らの首に突き付けてきた。そうして彼らは僕らの腕を後ろに回したかと思うと、縄で縛ってしまった。僕もケンも、屋台の主人と兵隊をにらむことしかできない。
「ふんっ」
屋台の店主はまた鼻を鳴らし、足元の星屑石を踏みつけた。星屑石は粉々に割れてしまった。兵の中の長と思しき人が何か言った。兵隊は用意した長い縄に僕らの手を縛り付た。そのまま前と後ろに分かれて囲んだかと思うと、長の掛け声を合図に行進を始めた。もがいて抵抗するも力かなわず、どんどん引張られてしまう。どうしたら良いのかわからず、僕はラウトが現れないかと後ろを振り返った。屋台の主人が兵隊の長から何かを受け取るのが見えた。隣を歩く兵がすかさず首に剣を突き付けてきた。僕は観念して前をみた。ケン、テラ、僕、ソウの順に、僕らは兵隊に追い立てられるまま進むしかなかった。そんな僕らを見つめていた目の存在を知ったのは、それからずいぶん後のことだった。
「親分!奴らが兵隊に囲まれていますぜ!」
屋台の一つで女店員に耳掃除をしてもらっていたリキは、その言葉に首を持ち上げた。
「あ、痛てっ!奴らって誰のことだ?」
耳かきが当たって痛みを覚えた耳を押さえつつ、リキは慌てて駆け込んで来たガリにたずねた。
「ほら、離され島の奴らがあそこで兵隊に囲まれているのでさ!」
ポンチョの話に女店員の膝元から起き上がると、リキはガリが指さす方を見た。屈強な兵士に囲まれているのは、紛れもなく離され島の子供達だった。
「奴ら、ここまで来ていたのか。リョウ、ケン、テラ、ソウ、皆いるな。いや、ラウトはどこに行った?」
リキは独り言のようにつぶやいた。
「奴ら、はめられたな。おおかた飯でも食って行けと言われたのだろう」
リキがため息をつく。
「あれは商売の裏で奴隷売買をしているとうわさになっている屋台の店主だよ。かわいそうに。あの子達も連れて行かれるのだね」
一緒になって見ていた女店員が何かを思い出すように顔をしかめてつぶやいた。
「親分、どうします?このままだと奴らは大変なことになりますよ」
ガリの問いかけにリキは返事をせず、成り行きを見ている。
「無理だな。あれだけ兵がいては助けるのは難しい」
リキはガリとポンチョから目をそらした。
「ああ、縄に繋がれてしまった。ああ、連れて行かれてしまうよ」
女店員が悲し気に言う。そして、恨めしそうにリキを見つめた。リキはその視線に気が付かないように背をそむけた。が、何かを考えるように首を左右に振ると、背中を向けたまま言葉を発した。
「ガリ、奴らを追え。連れて行かれる先を必ず見つけ出せ」
ガリは一瞬嬉しそうな顔をしてすぐさま離され島の子供達を追いかけて行った。
「親分、奴らを助けるのですね」
ポンチョも何気に嬉しそうだ。
「わからねえ。だが、俺達を救ってくれた奴らだ。何もしないわけにはいかないだろうよ」
「流石、海賊リキだね。強きをくじき、弱きを助ける」
リキの返事に女店員が話に割り込んだ。どうもこの女店員はリキの馴染みらしい。
「そんな格好の良い者じゃない」
リキは肩にしなだれかかった女店員の手を軽く払いのけた。
「あ、ラウトだ。きょろきょろしてるぞ」
ポンチョがラウトに気が付いて声を上げた。
「誰もいない」
ラウトは皆がいるはずの場所で途方に暮れていた。場所を間違えたのか。大勢の人が行ったり来たりしている中で、違う所に来てしまったのかと自分を疑う。いや、ここのはずだ。ここでリョウ達と別れたのだ。ほんの少し前のことなのだ。彼らには行く宛てがない。いなくなるはずがないのだ。ラウトは自分より背丈の高い大人達をかき分け、その辺りを走り回って仲間を探し続けた。だが、リョウ、ケン、テラ、ソウの誰一人見つからなかった。筏に戻って貝殻をお金に替えようとうろうろしている間に、彼らはまるで霧のようにいなくなってしまったのだった。ラウトは絶望してその場に膝をついた。その時だった。肩に手が置かれたことに気が付いて、ラウトは振り返った。その視線の先にはポンチョが、そして、その後ろにはリキが立っていた。ラウトは茫然として、目の前に現れた海賊達をただ見つめていた。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
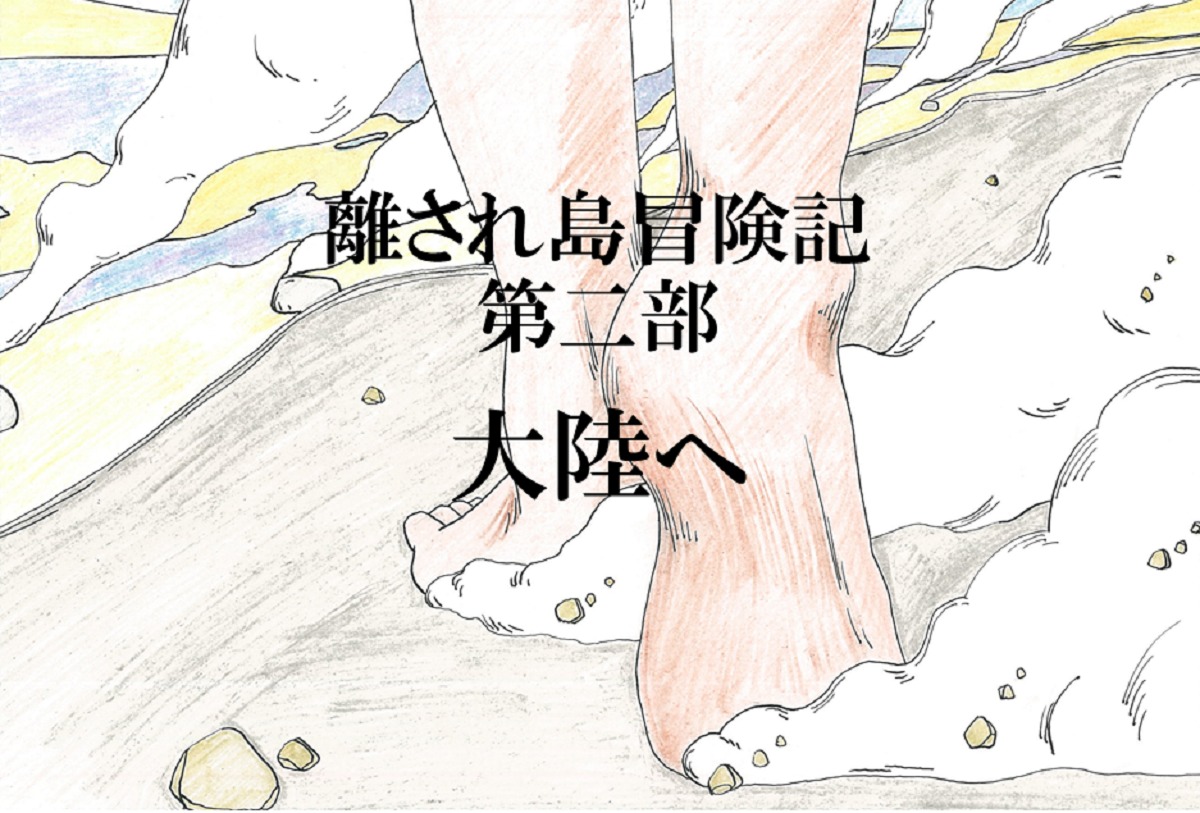


コメント