スポンサーリンク

「見たな」
ゆっくりと近づいて来ながらクレが言った。僕とケンは彼の気迫に押されて身動き一つとれなかった。異様な雰囲気を察して周囲の人々が僕らから遠ざかる。少し離れた所で丸く囲うように人垣ができた。一瞬の間これからの事を考えると、意を決して僕は口を開いた。
「なんのことですか?」
一歩前に出て、僕は真直ぐクレの目を見返した。クレは少しだけ首を傾げて、考えるような素振りを見せた。が、方針が決まったらしく歩みを進めた。
「まあ良い。四つん這いになって首を上げろ」
クレの目には難の躊躇もなかった。僕はケンの身体を後ろに押しやると一歩前に出た。
「彼は僕の後ろにいた。何も見えなかったはずだ」
「つまりお前は見たという事だな」
クレは即座に言い返した。
「ほんの数歩入っただけだからよくわからない」
「まあ良い。お前だけで勘弁してやる。しゃがめ」
クレは剣を頭上に構えた。僕はどうしようもないまま、ゆっくりしゃがみ始めた。足が震えるのがわかる。周囲の騒ぎは耳に入らなかった。その時、広場に飛び出してきたテラの姿が目の端に入った。コウとサイも後ろに続いている。
「リョウ!」
遠くからソウの声が聞こえた。巻き添えにしてはまずい。僕は急いで両手をついて首を持ち上げた。リキが砥ぎ師の手から研ぎかけの剣を取り上げるのが、人垣の足のすき間から見えた。
『そんな剣ではクレにはかなわないよ』
心の中でつぶやいた。何故か笑みがこぼれるのがわかった。クレが剣を振り上げた。
『ケン、後は頼む』
僕は目をつむった。高い山の裾野にある故郷の景色が、眼前に広がったような気がした。
「お待ちください」
一人の兵が駆け寄ってきた。
「彼らは良く働くし頭も良い。口も堅いです。いずれ重要な仕事を任せたいと考えていました。中にいたのはほんのわずかな間です。今回はご勘弁を」
仕事の割り振りを担当する兵だった。話がわかる人で、ソウやラウトについてのここ数日の配置も彼に頼んでいたのだった。
「ならん。勝手な動きをして、しかも我が住まいに立ち入ったのだ。許すわけがないだろう」
クレはあっさり断った。
「しかし…」
兵は食い下がろうとしたが、クレの冷たい視線に気圧されて下を向いてしまった。その時だった。
「クレ殿、王の使者が到着しました」
船着き場担当の兵が駆け寄ってきた。
「なんだと?」
クレはそちらの方に向き直った。
「急ぎ剣を調達したいとのことです」
続いて兵の口から出た言葉にクレは顔をゆがめた。しかし、すぐに気を取り直したのか、あっさりとこう言った。
「完成している剣を全て荷車に積め」
僕は何を言われているのかわからなかった。するとクレは、四つん這いになった僕の腹を思い切り蹴りつけた。続いてケンの頬を平手で叩きつける大きな音がした。
「お前達だ。こんな時に手慣れた奴を無くすわけにはいかないからな」
もだえ苦しむ僕に上から言葉を投げつけ、クレは王の使者を出迎えに船着き場に向かって足早に去っていった。その背中は二度と振り返ることはなかった。
「後は頼んだぞ。とっさのこととは言え、以後、勝手なことはしないようにな」
そう言うと、最初に駆け寄ってきた兵は踵を返して元来た方向に戻って行った。
「急ごう」
僕はケンに言った。
「ああ」
ケンはうなずいた。左の頬が薄赤く色づいているのがわかった。
「使者に揉め事を見せるわけにはいかないからな」
「運の良い野郎だ」
「使者に死者は会わせられないってか」
僕の首が落とされるのを見ようと集まっていた人々が口々に話しをしながら離れて行った。リキやソウの姿も既になかった。テラだけが遠くからずっとこちらを見つめているのがわかった。僕は恐怖に震えていたと悟られるのが嫌で、彼女と視線を合わせることができなかった。結局、軽く手を挙げて身振りで大丈夫だと伝えると、空いた荷車を取りに走り出した。
その晩、夕食が済むと、いつものようにソウはコウとサイの元に出かけて行った。重い米俵を代わりに運んでやるのだと意気込んでいた。ラウトは相変わらず力が出ないと、横になって寝ている。とぼとぼと歩くだけの存在になって幾日が過ぎただろうか。そんなラウトを心配しつつも、僕とケン、そしてリキは、白黒勝負で賑わっている方に足を向けた。
「心配していても仕方がない。なるようになるさ」
リキが言った。昼間のことについてはほとんど話をしなかった。一瞬のこととは言え、死を覚悟したのだ。今思い出しても足が震えてしまう。海賊としてこれまで幾度も同様の経験をしたはずのリキ。気持ちがわかるのか、何も言わずに僕らの後ろをぷらぷらと歩いてついてきた。昼間の緊張が痕を引いて勝負をする気にならなかった僕は、試しにリキに白黒を教えてみた。すると元来勝負事が好きなのか、リキは白黒にのめり込んだ。初めてのリキが有利になるように、先に石を沢山置かせての勝負開始。リキが勝てば次は石を一つ減らし、負けたらそのままという約束事にした。
「どうすりゃいいんだ?わからん、さっぱりわからん」
一手毎にぶつぶつ言いながらリキが石を置く。僕が彼の石を一気に沢山獲った時などは、大声を上げながら勝負の版をひっくり返すこともあった。それでは止めるかと問えば、やるという。毎勝負、大声を上げているリキに周囲の注目は自然と集まっていった。
「そろそろ止めようよ。あまりに遅くなると明日の仕事が辛いよ」
最後は僕が音を上げた。
「もう一勝負だけ」
リキの返事にため息が出た。その時、ふと、周囲が静かになっていることに気がついた。大騒ぎするリキに人集りができて、一手打つ度に野次が飛んでいたはずなのにどうしたことか。僕は周囲を見渡した。そして、背後に立っているクレの存在にその時になってやっと気が付いたのだった。
「ふん」
僕と目が合うとクレは鼻から息を吐いてから横を向き、静かに立ち去った。リキとの勝負に先ほどまでうっすらとかいていた汗は、その途端に冷たいものに変わった。僕の背筋は凍るように固まるのだった。
「ではあと一度だけ」
平静を装うようにリキに返事をしたものの、その勝負は僕の大負けとなった。帰り道、ご機嫌で話しかけてくるリキに少々うんざりして足が速くなった。リキは代りにずっと勝負を見ていたケンに話しかけた。
「初めてにしては強いのではないかな」
ケンのお世辞にリキは満面の笑みを浮かべた。
「よし、明日はケンと勝負だ」
リキの言葉にケンは笑いながら首を横に振った。
「僕は白黒勝負をしたことがないのさ」
ケンの言葉にリキは驚いてこう言った。
「え、その割には熱心に覗き込んでいたよな」
「うん、そうなのだ。嫌いではない。むしろ好きなのだと思う。ただ、手が思いつき過ぎて、一手も打てないまま勝負が進まなくなる気がするだけなのさ」
「へー、そんなもんなのかな」
ケンの言葉にリキは首を傾げるのだった。
翌日、船が到着した。そう、僕らが載せられてきた奴隷を運んでくる船のことだ。船上にポンチョの姿を見つけると、リキの口元に白い歯が覗いた。運ばれてきた奴隷が降りた後も、船はいつになくゆっくりと船着き場にとどまった。
そしてリキが鉄鉱石用の荷車を押して船の脇を通り過ぎようとした時だった。
「おーい、忘れものだ」
ポンチョの声がして細長い箱が空中を飛んだ。箱は見事にリキの荷車に着地した。あまりのさりげなさに兵は誰一人この事に気が付くことはなかった。準備は整った。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
別バージョン
最初に戻る
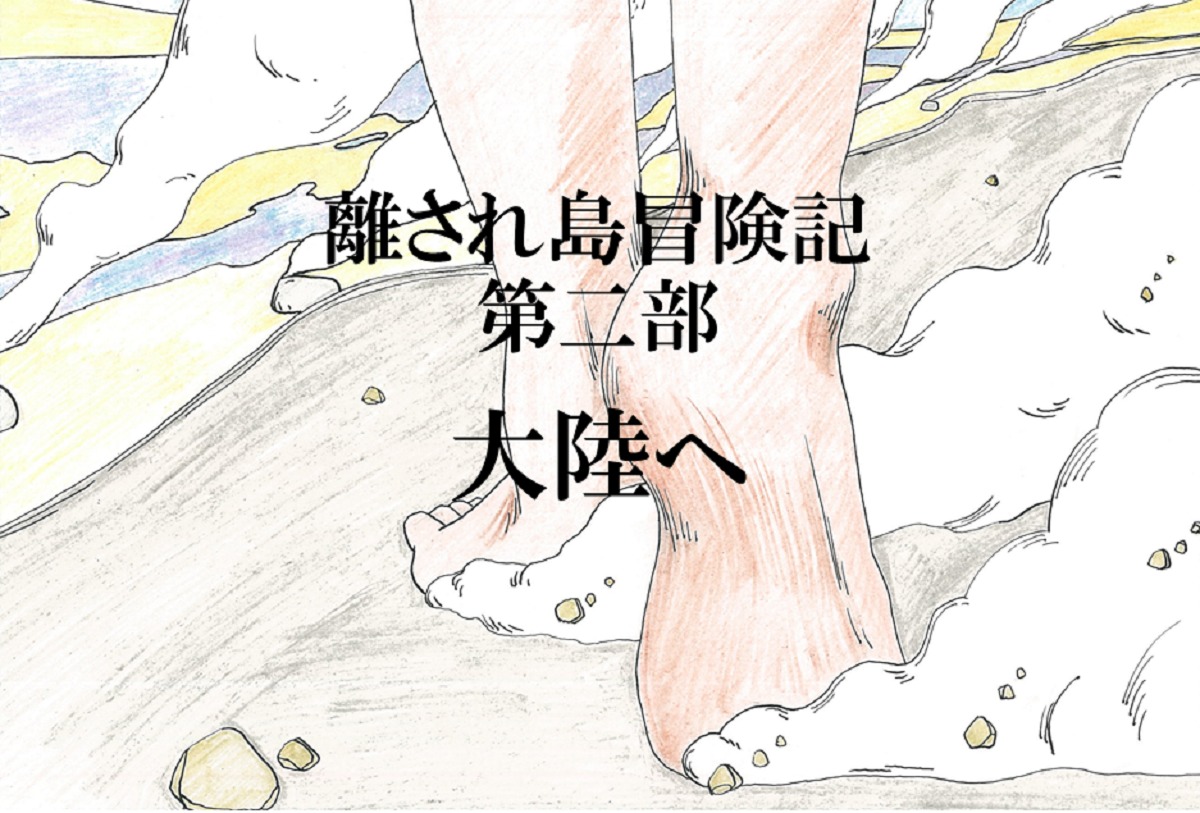

コメント