スポンサーリンク

ケンの次の手は決まっていた。いや、決まっているはずだ。ここで右上隅に手を入れないでいると、そこにある石が飲み込まれてしまう。それはつまり、最初の一手を否定することになるのだ。そうなれば、右上の広大な場所が丸々クレの陣地となってしまう。言うまでもなくケンの負けは確定だ。ケンの右手が動いて白石が摘まみ上げられた。一息ついて後、その石は右上隅の補強に回った。これでそこの石は安全になり、わずかではあるものの右下に続いて右上でもケンの陣地は確保された。僕はほっと一息ついた。間を置かずクレが次の手を打った。元から左上隅にある黒石から一つ空けた所に堂々と置かれたその石は、左上隅の権利と上辺の優位を主張していた。ケンの先手、クレの後手で始まったこの白黒勝負は、ここに来てようやくクレ主導の展開になったのだ。クレの顔も自信に満ち溢れていた。
「星だ。星が見える」
後から聞こえた声に僕は驚いて振り返った。つい今しがたまで自ら歩くことも出来なくなっていたラウトが言葉を発したのだ。先ほどまでのうつろな表情はどこへ行ったのやら。ラウトの目には光が宿り、右腕は夜空に向かって突き出されていた。ラウトは人差し指で星の形をなぞる仕草をした。普段は炭焼きや鉄作りの煙が充満して、星どころか、月すらも滅多に目にすることができないこの鉄炉。だが、ケンとクレの勝負を見る為に鉄炉中の人々がここに集まったことで、夜通し行われるはずの作業が止まってしまったのだ。鉄炉を満たしていた煙は川風に流されてすっかり消え、今、満天の星が僕らを見下ろしていた。
「リョウ、もう大丈夫だ。怖いことなんてない」
ラウトの言葉に僕は何度も首を縦に振った。嬉しくて何も言うことができなかった。
「ラウト、気が付いたのだね」
ケンが後ろを振り返りラウトに声をかけた。ラウトは自分の力で上半身を起こして、ケンに向かって大きくうなずいた。
「星が僕らの居場所を教えてくれた。僕はわかる。帰る道筋が僕には見えるのだ」
ラウトの返事に笑顔になると、ケンは夜空を見上げた。
「久しぶりだな、星を見るのは」
正面にいるクレの存在など気にもならないかのようにケンはつぶやいた。先ほどまでの表情とは打って変わり、ケンの顔は活き活きと輝いていた。そして一呼吸すると、盤上に集中するべく視線を下げた。
「どこにでも星はあるということか」
盤を見つめながらケンが言った。
「何、何を言っている?」
急にくつろぎを見せ始めたケンに対して、訝し気にクレが問いを発した。
「鉄炉には星がないのだと思い込んでいたのだ。でもそうではない。ここにも星はある。生きる道はあるということさ」
クレを真直ぐ見返すとケンは言った。
「ならば、どう戦う?」
クレはにやりとして言った。形勢に自信がある証拠だった。ケンはクレを無視してやおら新たな白石を置いた。左下隅の石から二歩進んだ場所。そこに勢力を広げようと言うのだ。出来ることをコツコツ積み上げる、そんな無理の無い手だった。それほど広い範囲ではないものの、この手によって左下隅にもケンの陣地が築かれようとしていた。クレはケンが置いた石の斜め隅に続く手を放った。ケンの陣地を低く小さく制限しつつ、残る中央の広大な土地を手に入れようというのだ。対してケンの手も中央に向かって伸びた。クレもまた、すぐさま一つ飛んだ点に石を置く。まるで、中央を支配するのは俺だと黒い石が言っているようだ。盤上における勢力図は、はっきり黒に傾いていた。周囲にいる誰もが、ケンに勝ち目はないと思い始めていた。その時だった。左上、上辺、左辺、そして中央と、黒が大きく模様を描いている中に一つの白石が置かれたのだ。
「おお!」
周囲の人々が沸いた。隅の方で小さく生きを狙った手であれば、このような歓声が上がることは無い。だが、漆黒の闇に包まれたようにも見える、上辺中央の高い所にその白石は輝いていた。
「既に我が領地となりかけたその場所で、生きようというのか」
クレの目は憎々し気に揺れ動いていた。
「うん、だってこんなに広いのだもの」
「本当に生きられると思っているのか」
「例え王であろうとも、夜空の星を消し去ることはできないと今わかった」
声にならない二人のやりとりが、リョウの耳にも届いていた。クレとケン、それぞれの思いが火花となってぶつかり合うのが目に見えるようだった。ここからが本当の闘いだ。リョウも、周囲を取り囲む鉄炉中の人々も、固唾を飲んで勝負を見守った。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
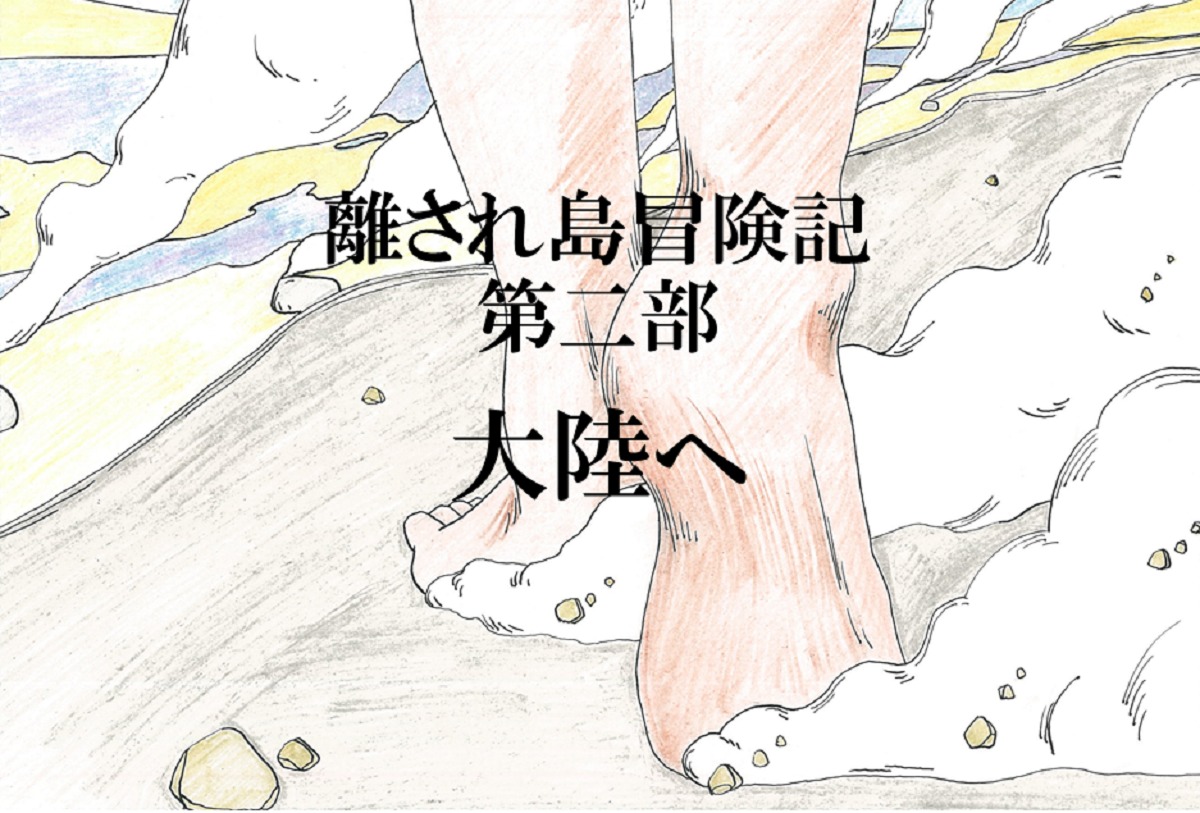

コメント