スポンサーリンク

「夜明けまでだ。それ以上は待てない」
船長がリキに向かって言った。
「そうだな。夜が明けたら、その時は出発だ」
リキが同意する。
「何故だよ?リョウ達はきっと来るよ。それまで待ってくれよ!」
ソウが激高して言った。
「鉄炉へ行く船がこの船を見かけたら必ず通報される。つまり捕まって全員死ぬということだ。それだけは避けなければならない。わかるだろう」
リキの言葉は重かった。ソウはそれ以上反対することもできず、ただうなだれるしかなかった。テラはソウに近寄って肩に手をおいたが、その顔色はソウ以上に暗かった。来る運命を受け入れることで生き延びてきたコウとサイの幼い姉妹は、船縁に寄り添うように座り込んで身じろぎ一つしなかった。あるいは眠っているのかもしれない。この後どうなるか、考えてわからないことは考えない。そんなことよりは、休める時は休もう。コウがサイに耳打ちした言葉は、テラの耳にだけ微かに届いていた。同じように、ガリとポンチョの二人も甲板に転がっていびきをかいていた。皆がそれぞれの思いを胸に、夜明けまでの時間を過ごしていた。
昼間は熱い大陸の地面も、夜中となると冷え切っていた。地面の冷たさを感じながらリョウ、ケン、そしてラウトの三人は東に向かって歩いていた。空が白みつつある。
「待っていてくれるかな」
「そう願いたいね」
「大丈夫だよ、きっと」
三人は互いを励まし合いながら歩みを進めた。やがて河岸に降りられそうな坂道が見つかった。
「降りよう」
「うん」
なんとか一人で歩けるように回復したケンを真ん中に、三人は崖とさして変わらない急な坂道をゆっくり降りて行った。大きな岩が目の前に現れた。そして、岩陰に隠れるようにして停泊している船が三人の目に入った。
「良かった。待っていてくれたのだ」
その言葉と時を同じくして、朝日が周囲を明るくした。真横からの光に、三人の影が河岸に長く伸びた。影に気が付いてくれたか、船上から橋桁が降りてきた。
港までの数日間で、大陸の状況は大きく変わっていった。
「反乱が起きた」
途中の船着き場では、そんな言葉が小声でささやかれるのだった。
「次の王を名乗る者が何人も現れたらしい。クレもその一人だという」
船長はリキに、リキはリョウに耳打ちし、やがて船に乗る全員がその情報を共有するのだった。
「鉄炉がどうなっているのかもわからない。次の仕事を探さないとな」
船長が船員に話したのは、対岸が見えない程に河幅が広がり、懐かしい海の香りがし出した時だった。船を降りる時が来たのだ。港に着くとガリがどこかに走って行った。やがて、ガリに連れられて一人の女性が現れ、リョウ達の筏まで皆を案内してくれた。筏が壊れたり流されたりしないように度々見に来てくれていたという。ラウトが言うには、リキの恋人らしい。市場で食堂を切り盛りするこの女性は、出入りする船員達とやり取りする関係で世情に長けていた。リキが鉄炉の事情に詳しく、リョウ達の逃亡計画を立てられたのも、この女性が情報を集めてくれたお陰だということだった。
「戦いが起きたよ。この先どうなるかわからないから、さっさとお逃げよ」
女性は言った。やはり王は倒れ、大陸中がごった返すような騒ぎらしい。
「僕らがあっさり鉄炉から出られたのも、そういう事情があったのかもしれないね」
ケンの推測は皆の腑に落ちるものだった。コウとサイの二人が増えたことで筏は手狭だった。どうするかと相談していると、リキが舟を出してくれるという。
「離され島で助けてもらった恩返しのつもりだったが、結局、お前達自身で鉄炉から抜け出したんだものな。もう一度くらい手助けするぜ」
リキ達の有り難い提案を僕達は受けることにした。海賊が道案内してくれるのだ。こんな心強いことはない。
「ソウ、お前、海賊になる気はないか?リョウとケンは戦いとなれば役立たずだが、お前は強いからな」
リキの言葉にソウは目を輝かした。リキ、ソウの腰には、クレからもらった剣が下がっていた。戦うものとしてすっかり一人前になった気にソウがなるのも無理はない。もちろんテラがソウの耳を捻って止めた。なんだかんだと仲の良い姉弟の様子に皆大笑いするのだった。
リキ達海賊の舟が最初に岸を離れた。ソウ、コウ、そしてサイも一緒に乗っている。すぐに筏も続く。リキの恋人は見えなくなるまで手を振り続けてくれた。
波しぶきが頬を濡らした。懐かしい潮風を操って、筏は進む。テラが鼻歌を歌っている。長い遠回りとなった鉄炉での生活を離れて、故郷への道を進めるのがよほど嬉しいのだろう。
「…、リョウ、リョウ」
何度か後ろから呼ばれたのに気が付いて、僕は振り向いた。ラウトとケンが、帆と櫓を操ってくれていたので、前方を見ながら物思いに耽っていたのだ。
「村に帰ったら、旅をしなくて済む方法について皆に話すのでしょう?」
声の主は、先ほどまで歌っていたテラだった。テラの人差し指は、僕らの腰に下げられた剣を指していた。
「うん、そうできれば良いと考えているよ」
僕は答えた。村の特産品である星屑石に取って代わる物。それが鉄であり、鉄から作り出す剣と道具だと僕らは考えているのだ。鉄は丈夫で切れ味が凄い。例え加工しやすくともすぐ壊れてしまう星屑石とは比べようもない。自分達で鉄製品を作れるようになれば、新たな生活の糧となるのではないか。僕とケンは度々そんな話をしていた。簡単なことではない。先ず原料である砂鉄を探すことから始めなければならないからだ。
「リョウならきっと出来るよ」
テラは笑った。僕はとっさに日差しをさえぎるように手をかざし、下を向いた。常に煙が充満していた鉄炉に慣れた目に、大海原で受ける日差しは強すぎた。そして、久しぶりに見るテラの満面の笑顔は、それにも増して眩しかったのだ。
「やるよ、やってみせる」
僕は心に誓った。波間に目を戻すと、遠く海の向こうにある故郷の山が見えたように気がした。
第二部完
第三部につづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
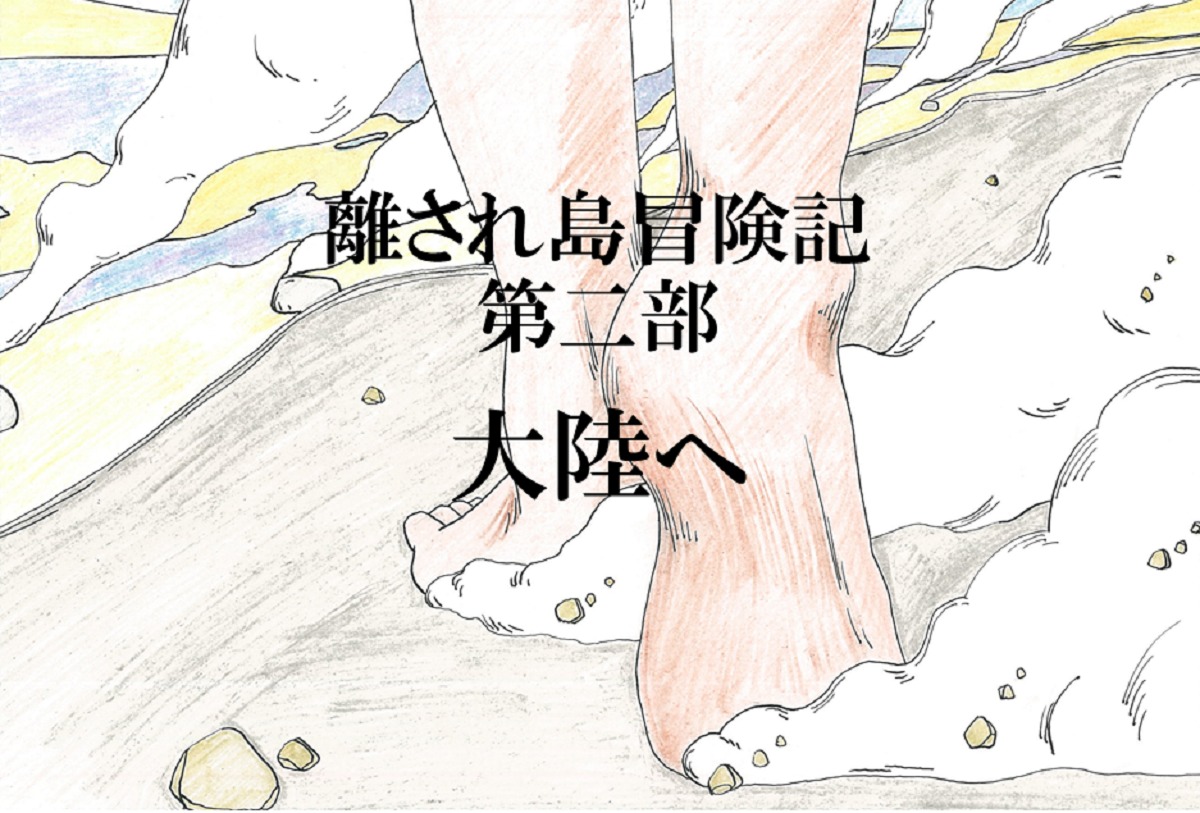

コメント