スポンサーリンク

米が実る草は稲と呼ばれていた。草取りをしながら僕らは米の育て方を教えてもらった。一緒に働いているうちに頼りにしてもらえるようになったらしく、田んぼの修繕も手伝うことになった。田んぼを囲む堰は畦と教わった。
「助かるっち」
額の汗をぬぐいながら彼は言い、途中しばらくいなくなったかと思うと、笹の葉の包み物を持って現れた。包み物は僕ら全員に渡るだけの数があった。
「一休みするっち」
彼は木陰に僕らを案内してくれた。包みを開けて見ると、それは米を炊いて握った物だった。
「握り飯、言うっち」
少しだけしょっぱい握り飯を僕らは頬張った。疲れた身体に嬉しい美味しさだった。喜んで食べる僕らの前に竹筒に入った水が置かれた。乾いた喉に水が行き渡り、力が湧いてくるのがわかった。もちろん、その後の仕事がはかどったのは言うまでもない。その日、僕らは日暮れまで田んぼで過ごした。良かったら一晩泊っていけという有り難い言葉を丁重に断って、そこを後にした。それには理由があった。ソウが持っていた籾を彼に見てもらったところ、もう時期を過ぎているかもしれないが、すぐにでも土に蒔いた方が良いと言われたからだった。やはり少しでも早く村に帰らなければならないと皆が思いを強くしたのだった。
「米はとにかく雑草との闘いだ。人ができるのはそれだけかも知れん。最大の敵は虫、そして雨が降らないことだが、それは俺達ではなんともならないからな」
別れ際、彼は言った。珍しく土地の言葉を使うことなく、大事なことを伝えてくれようとしたのだった。
「遠くに行くようだけど、困った事があったらいつでも来いっち」
彼の言葉に僕らは顔を見合わせた。疑われ疑うところから関係が始まる大陸での経験と全く違ったからだった。相手を信じることから始まったこの土地での出来事は、自分達の居場所に戻って来たのだという思いを僕らの胸に湧き出させてくれた。暖かいものがこみ上げてくるのを感じながら、その時はお願いしますと僕らは頭を下げた。
「俺は、ナゴって言うっち」
そう言って彼は笑い、夕暮れの中、見えなくなるまで見送ってくれたのだった。僕らはその名前を忘れないように心に刻んだ。
スポンサーリンク
翌朝、食事を終えて出発しようとした時のことだった。ちょっと待ってとテラが言ったかと思うと、脇にあった竹筒を手に近場の森に走って行った。すぐ戻って来るとのんびり座っているソウに向かって手を出してこう言った。
「ソウ、お米かして」
突然の話にソウは訝し気な表情となったが、姉の命令に従って懐から籾を取り出した。テラはその籾を受け取ると竹筒に入れて、今度は河岸に走った。中に水を入れているようだった。全てが終わって僕らは出発した。筏を繋いでいた岩から綱を外す。ケンとラウトが上手く櫂を操ってくれたおかげで、難なく海に漕ぎだすことができた。周囲に岩が無くなったため、帆を上げた。南からの暖かい風を受けて、帆が膨らみ、筏は一気に進み始めた。こうなれば、後は岸から離れ過ぎないように気をつけさえすれば良い。のんびり風任せの気ままな海旅となった。とは言え、以前に比べてコウとサイ、そしてソウが余計に乗っている分、筏上はやや混み合っている。座ることはできても寝転ぶにはちょっと狭いなとソウが不満を漏らす。気にはなるものの、致し方がないことだった。その狭い筏の上、皆をかき分けるようにして僕はテラの隣に移動した。ずっと同じ筏に乗っているのにも関わらず話すのは久しぶりのような気がする。少し緊張しながら僕はテラの横に座った。
「ん?リョウ、どうしたの?」
竹筒を覗き込んでいたテラは顔を上げて、不思議そうな顔をした。
「うん、さっきの籾、どうするのかなと思って」
僕の問いに、テラはにんまり笑って竹筒の中をこちらに向けた。中には焦げ茶色の土が詰まっている。
「ナゴさんが、植えるには遅いかもしれないって言っていたでしょう。村に着くまで待っていたら絶対間に合わないから、この竹筒で私が稲を育てることにしたの」
見開かれたテラの目は決意に満ち溢れていた。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
前話に戻る
1話に戻る
第二部1話に戻る
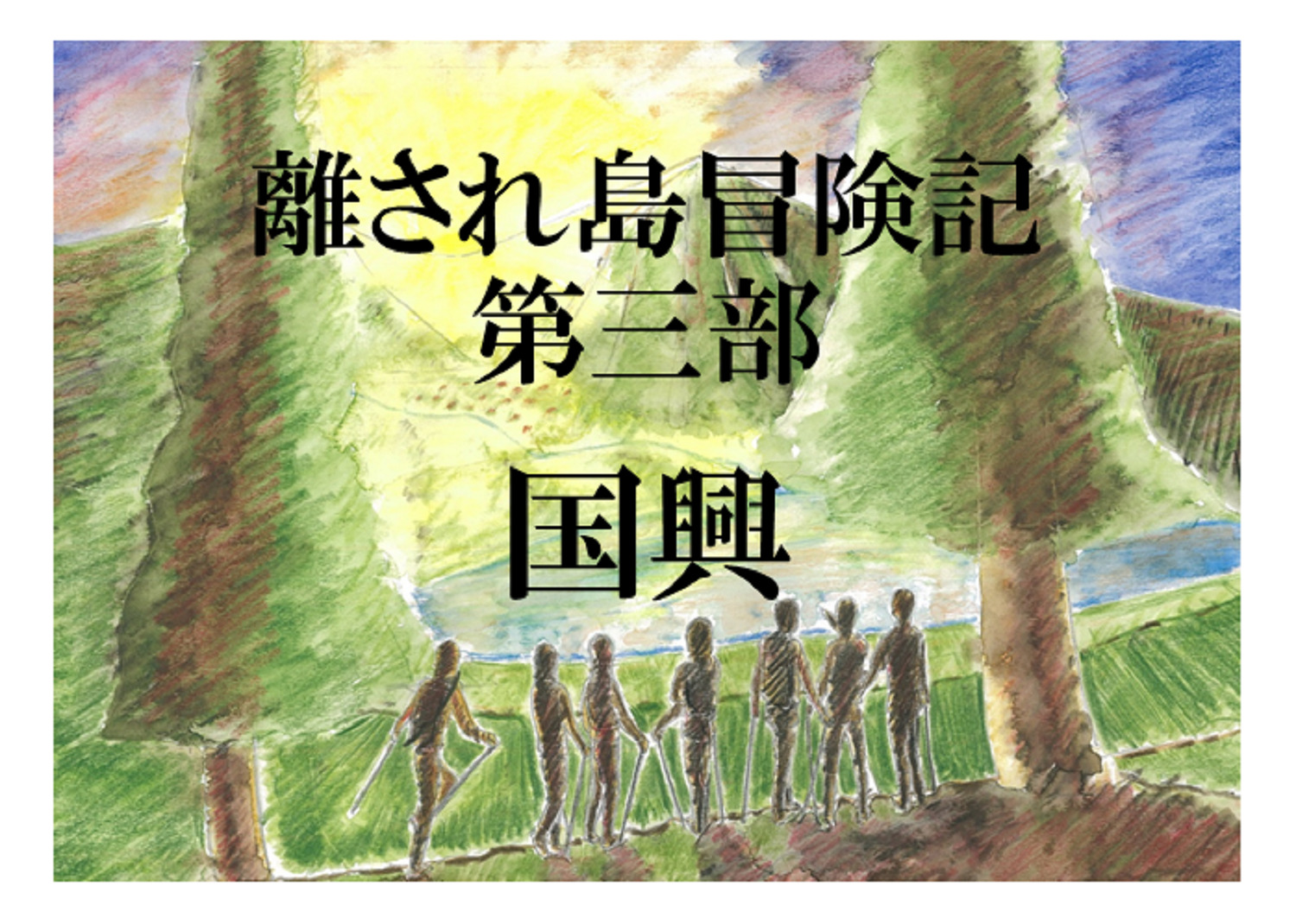

コメント