スポンサーリンク

大陸の鉄炉では、下端の兵が持ついわゆる濫造した剣と、位の高い者が持つ剣とでは、造る場所も人もはっきり分けられていた。謹造の剣は土壁で隔てられ、人目に付かない場所で造られていた。つまり質の高い剣の作り方は秘められていたのだった。濫造品を作っていた僕らが、ある意味、命がけで目にした謹製品を造る様子。火の色は、明らかに濫造のものより低く、そして、赤く熱せられ、既に形が整えられた剣は、そのすぐ前に座る男が手に持つ槌によって何度も叩かれていた。謹造の剣は、棒状になった鉄を溶けない程度に熱して柔らかくしたうえで、叩いて形を整えているように僕らの目には見えた。対して、普段僕らが造っている濫造品は、熱い火でどろどろに溶かした鉄を型に流し込み、冷めた後、鋭く研ぐだけの単純作業だった。言うまでもなく濫造剣と謹造剣では造り方が違うのは明らかだった。
スポンサーリンク

龍ヶ淵での剣造りは、砂鉄を溶かして鉄にするところから始まった。鉄ができると、僕らは手始めに棒状の型に鉄を流し入れた。そして一旦冷ました後、火にくべて赤く柔らかくなったところを槌で叩いてみたのだった。大陸で僕とケンが見た、槌で叩きながら剣を造る手法。この叩くという作業がどのような効果をもたらすのか、僕らは未だわかっていなかった。だからやってみるしかないのだった。実際に叩いてみると、鉄の棒は所々にひびが入り、ばらばらになってしまった。一つ一つ見てみると、鉄質が低くて割れやすいところと、粘り強い剣に向いた部分があることがわかった。叩くことで、良質の鉄とそうでないものの判別ができるのだ。考えた末、改めて鉄で平たい道具を僕らは造った。そして、割れてしまった質の低い部分を取り除き、残った粘り気のある鉄をその道具の上に綺麗に並べて熱してみた。赤くなった鉄を叩いてみると、ばらばらの鉄を並べたものであっても、くっつけることができることがわかった。何度も失敗を繰り返した後、僕らはそれらしい剣をいくつか造り終えた。ソウやラウト、コウとサイ、そして、ケンの弟妹であるシュウとハナも歓声を上げて喜んでくれた。しかし、僕とケンの口からはため息だけが漏れていた。大陸の鉄炉を出る時にクレからもらった謹造剣と、今回できた剣を合わせてみると、僕らが造った剣ははっきり弱かったのだ。折れず、曲がらず、よく斬れる。それが理想の剣だとすれば、謹造剣は極めて理想に近く、僕らの剣は足元にも及ばないのだった。龍ヶ淵はすっかり雪景色となっていた。冬前に淵の底から取った砂鉄はなくなり、炭は底をついた。僕らは剣造りを一旦諦め、食べ物と炭にするための木材集めに雪の中を歩き回らなければならなかった。
「リョウ、雪ウサギだ」
隣りにいたケンがささやいた。僕は、手にした弓を構えて矢を放った。矢はウサギに当り、夕餉の材料を僕らは手に入れた。
その晩、ウサギの皮を剥ぎ、肉を削いで土鍋に入れた。雪を掘って採ったセリも入れて煮込む。皮はもちろん、なめして防寒具として使う。コウが星屑石で皮に残った油を器用にそぐ。そして、夕餉が出来上がるのを待つ間、器用になめし始めた。コウもサイも、山の生活にすっかり馴染んでいた。
「うん、旨い」
皆で食べ始めると、ラウトが言った。当初魚しか受け付けなかったラウトも、最近は肉の味に慣れてきたようだった。
「なあリョウ。このウサギを獲った矢は、鉄で造った鏃を付けてあるのだろう?」
ソウが言った。
「うん、そうだよ」
小さな鏃なら、僕らは造れるようになっていたのだった。
「充分なのではないのかな?」
ソウが炉の火を見つめながら言った。
「うん。そうかもしれない。でも…」
今までのことを考えれば、鉄で鏃が造れるようになっただけでも村の生活がしやすくなることは間違いなかった。僕らは村の集会で鉄製品をお披露目する時に、自分達で造った物ではなく、手取り早く大陸から持ち帰った剣を使ってしまった。何故、そんなことをしてしまったのか。ソウに指摘されるまでもなく、未だ造り方のわからない剣の存在が僕の肩に重くのしかかっていたのだった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
前話に戻る
1話に戻る
第二部1話に戻る
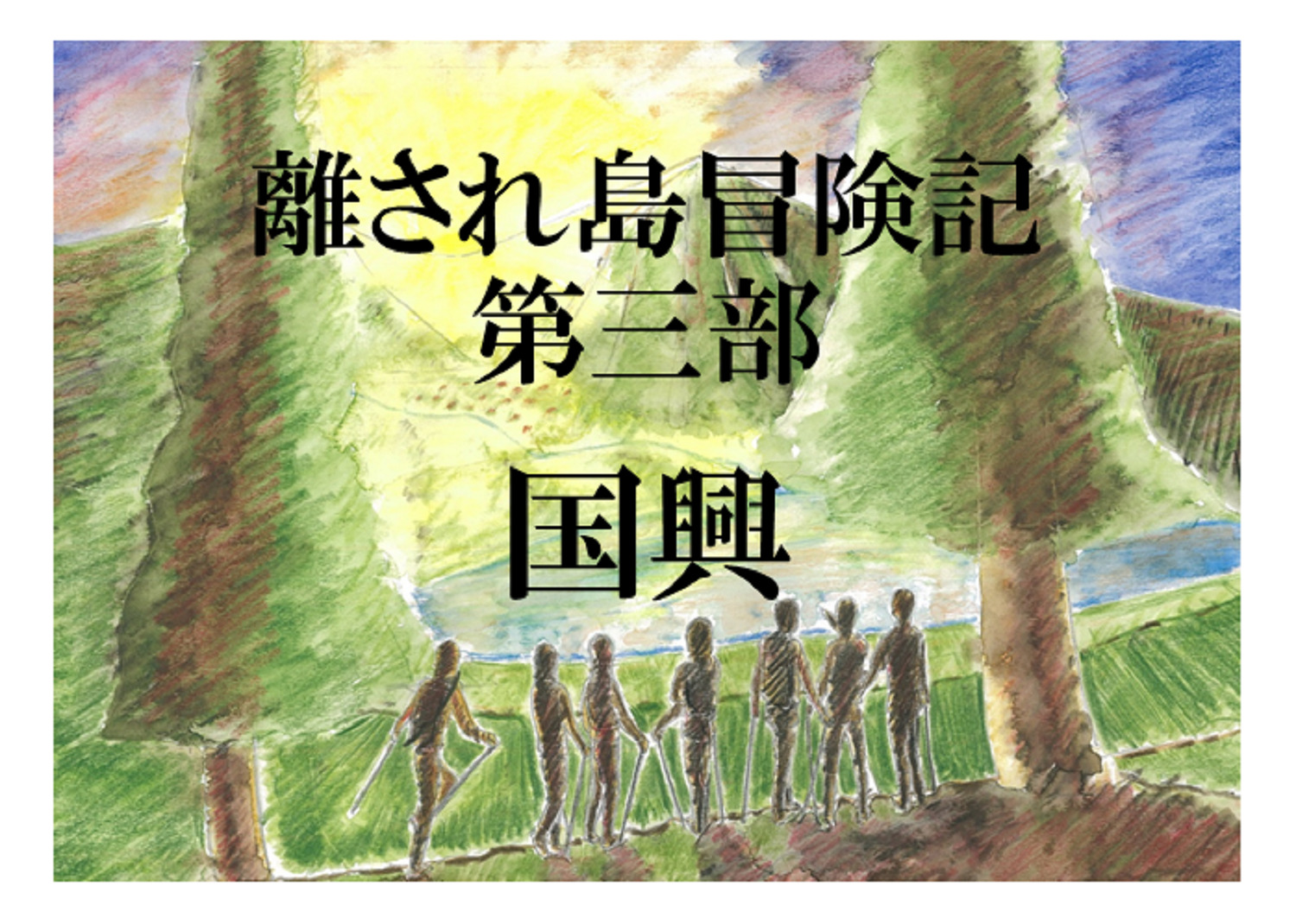

コメント