スポンサーリンク

鉄炉とは鉄の原料を溶かす炉のことなのだけれど、僕らがいる場所そのものが鉄炉と呼ばれるようになっていた。鉄炉は西から東に流れる大河の北岸にあった。原料となる鉄鋼石という鉄の混ざった石。鉄をむらなく扱いやすい状態にするために使う石灰という白い土。この二つは船で運ばれてくる。船から鉄炉まで運ぶ手間を極力少なくするために、鉄炉は河沿いに位置しているのだ。この場所の上流側と下流側は煉瓦で造られた壁で囲まれている。煉瓦とは粘土を四角く固めて焼いたもので、作り方は土器に似ていた。この壁は容易には乗り越えられないほど高く作られている。残る北側は高低差のある河岸の崖で、言わば天然の壁だ。崖の一部は人が昇り降りできるように削り込まれているものの、上がり口は柵で覆われていると共に常に二人の兵で守られている。ここにいる僕らが好きなように出入りすることはもちろんできない。つまり僕らのいる鉄炉は南側を大河が流れ、西と東は煉瓦の壁、北側を崖で囲われた要害なのだった。強固な守りには二つの理由があった。一つは鉄と剣を盗まれないようにすること。もう一つは作業する人々が逃げ出さないようにするためだった。
さて、鉄を作る上でもう一つ大事な材料がある。それは炭だった。鉄炉の中で鉄を溶かすには大量の炭が必要だ。炭を作るには材木がいる。その材木は崖の上に広がる森の木を伐採して運んでくるのだった。朝、切り出す役割の人達が崖を上がって行く。鉄炉での全ての作業の中で、ここに最も多くの人が割り当てられる。炭が無くなっては何もできないからだ。崖を上がった人達はそのまま森まで進み、木を切り倒し続ける。そして、夕方になると揃って降りて来るのだった。倒された木はいくつかに切り分けられて台車に載せられる。台車は牛という足が四つある生き物に引かれて段丘の際まで運ばれる。そこで材木の両端を縄で縛って鉄炉のある河岸まで降ろす。材木はそこで薪にされて炭焼き小屋に入れられる。毎日がその繰り返しだった。森の中で炭にした方が軽くて運び易いようにも感じるものの、壁の無い場所での作業は少しでも減らしたいがためにこのような手順がとられているのだった。結局のところ、森での木の伐採だけが壁に囲まれていない場所での作業なのだ。次から次に移ろいゆく伐採地の全てを予め壁で覆うことなど、できはしないからだ。その代わり木を伐り出す人達には必ず多くの兵がついていて、逃げ出さないように見張っているのだった。夜中の作業がないのは、他の仕事と違って火で照らさなければならない範囲が広すぎるためだろう。伐採地を隈なく明るくすることに薪を使うなど、炭作りの中では本末転倒もはなはだしい。それに予め組み立てなければならない炉や炭焼き小屋と違い、人数を増やせばその分木材の切り出し量も増えるという単純な理由もあるだろう。人も物も、何から何まで良く考えられて配置されている。それが鉄炉だった。その全てが主であるクレの仕業だとすれば、恐るべき頭脳だと言えるだろう。
一つだけ懸案があった。鉄炉のすぐ近くにあった森は既に伐りつくされていて、今は少し離れた所にある森から木材が運ばれてくる。他の材料に比べると手間がかかるのだ。そのことについて仲良くなった炭焼きの長に訊ねてみた。
「鉄炉は以前、この河のもっと上流にあったのだよ」
彼は言った。
「木を伐り、炭を焼く。瞬く間に周囲の木が無くなっていく。見渡す限りの森の木を採りつくす。すると新たな森を求めて鉄炉は河を下る。残るのは君達がいつも目にしている黄色い大地だけなのだ」
続けて小さな声でつぶやいた後、炭焼きの長は咳き込んだ。長年、炭焼き小屋から出る大量の煙を吸い続けた為か、彼の喉は潰れかけていたのだった。それほどに昼夜違わず出続ける煙は、常に僕らの周囲を取り巻いていた。太陽の光は薄らぎ、月と星の輝きもここでは目にすることはできなかった。
僕はケンに向かってため息をついた。
「この煙。それに木が無くなる度に鉄炉を移動しなければならないとなると、旅をしなくて済む方法とは相容れないことになる。問題だな」
するとケンは意外そうな顔で振り返った。
「リョウ、何を言っているのだい?そんな問題、初めから解決しているではないか」
ケンの瞳に、僕は夜空の星々の輝きを見る思いがした。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
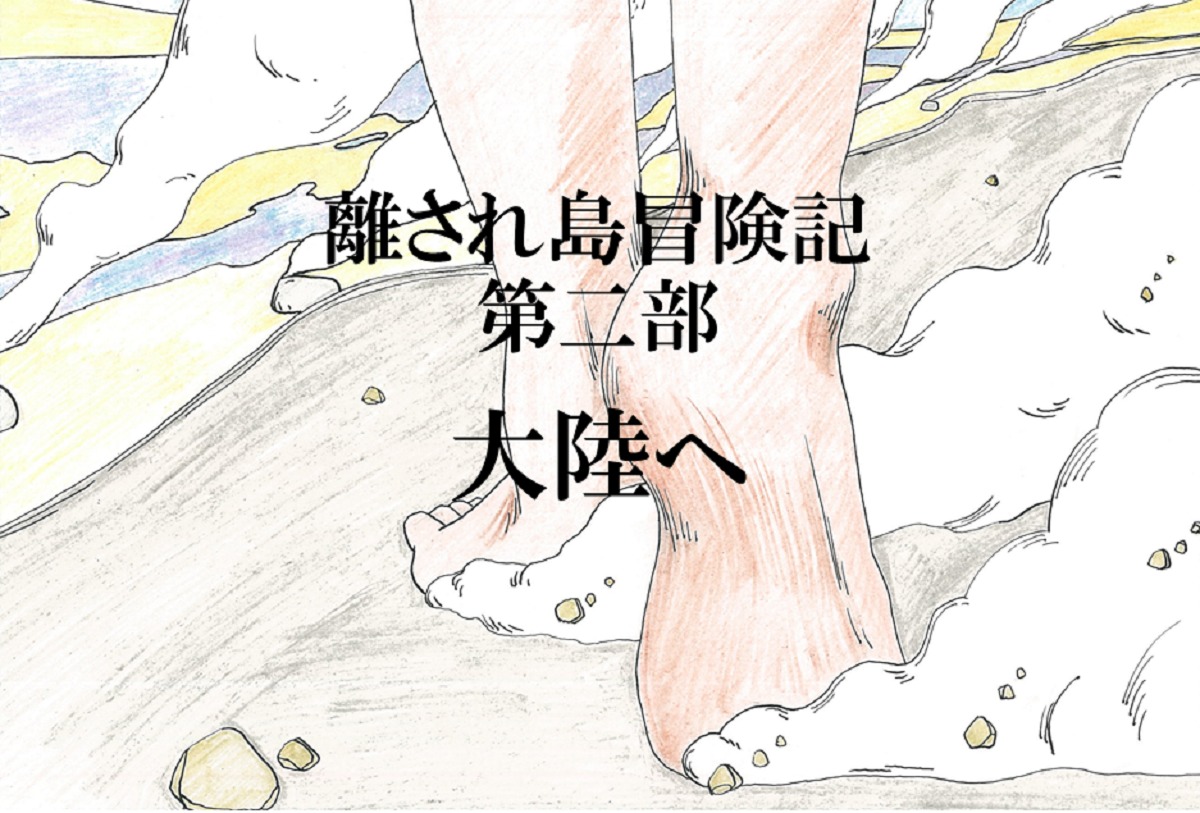

コメント