スポンサーリンク

「私達も手枷をつけられてここに来たの」
コウは言った。サイは小さかった頃のことをあまり憶えていないらしく、曖昧にうなずくだけだった。二人がここに来た理由も僕らと大差なかった。お腹が空いて倒れそうになっているところをだまされて連れてこられたのだ。
「でもここに来て、私達は幸せだと感じたの」
続いてコウの口から発せられた言葉に僕らは声を失った。テラがコウとサイをそっと抱きしめた。幼い少女達の生い立ちに心を痛めて、姉のような気持になっているのだろう。朝から晩まで働かされ続けて、気を失うように眠りにつく彼女達の生活を僕らは目にしていた。もちろんそれはテラも同じなのだけれど、今だけのことと考えているテラと、行く宛てなく鉄炉で生きていくしかない二人の姉妹とでは辛さの重みが違うのだった。
「お父さんとお母さんのことはわからない。戦いが起きてはぐれてしまったの。食べる物も飲む物も無い。沢山の人が兵にやられるのを見たわ。それに比べたら、毎日食べる物があって、何より生きていられる。今の私達は幸せ」
僕達が考えもしない大変な状況を生き延びてきた強さが、コウの言葉にはあった。戦いに必要な武器を作る場所として鉄炉は守られていた。だが、ここから一歩出たら周囲に広がるのは攻め込み、攻め込まれる場所。やすらぎを求めることなどできはしない。違う姿をした、違う言葉を話す人が大勢いる所。もちろん良い人も沢山いる。だが、疑うことから始めなければならない土地。それがここ、大陸なのだった。
「コウとは手枷のことなの。仕事を覚えるまで私達は手枷をつけたままだったから、皆が自然とそう呼ぶようになったの。サイも同じ意味。呼び名が一緒だと困るから私がつけたのよ」
顔を上げてほほ笑むコウとサイ。その視線を真直ぐ見返すことが、僕にはできなかった。
「できるだけ早くここを出よう。その時はコウやサイも一緒だ」
次の晩、テラが夕食を配りに来た時に僕は三人に小声で話しをした。テラとソウは即座にうなずいた。ケンだけがすぐには首を縦に振らなかった。
「一つだけ知っておかなければならないことがある」
ケンが言った。僕らはケンを見返した。僕は鉄の作り方はほとんど覚えたと思っていた。これ以上、鉄炉にいる理由は無いに等しい。どうやってここから脱出するかを皆で考える時なのに、果たしてケンは何を知りたいのだろう。訝しんだ僕らは、続いて出てくるのであろうケンの言葉を待った。
「クレの住まいを囲う土壁の中。あそこには、僕らの知らない何かがあるはずなのだ」
鉄炉では時々、作られた剣の切れ味を試す試技が行われていた。沢山作られた剣の中から一本を選び、動物の皮や木材、それに防具に見立てた薄い鉄板などを試し切りするのだ。剣は刃こぼれするのは当たり前、折れてしまうことも珍しくなかった。最初、僕らは弱い剣を作ったことに対して罰が下るのかと恐れを感じた。だがそうではなかった。試技の最後にクレが出てきたかと思うと、自らの剣で同じものを切って見せるのだ。その切れ味は凄まじかった。刃こぼれ一つせず、全てのものを一刀両断するのだった。切り終わった後クレは、鉄炉で新しく作られた剣と自らの剣を見比べて一言つぶやくのが常だった。
「まあ、良い。大量に作るとはそういうことだ」
そして剣を高く掲げると、
「この剣がほしい奴は俺と勝負しろ。剣、白黒、どちらの勝負でも受けて立つぞ」
言い終えると高らかに笑い、身をひるがえして土壁の中に消えていく。それが試技が行われた時のクレだった。僕らは既に理解していた。これは出来上がった剣を試すために行われるのではない。クレが持っている剣にはかなわないのだということを皆に知らしめるためのものなのだ。出来上がった剣を奪っての反乱など起こしても無意味だと、鉄炉で働く者全員が試技のたびに胆に銘じるのだった。
「すぐ折れる剣で勝負を挑む者などいるものか」
「白黒でクレに勝てるものなど、この世に存在するわけがない」
作業を止めて試技に立ち会っていた人々は、口々に呟きながら持ち場に戻るのだった。
クレの住まいを囲う土壁の中からは、カーン、カーンという、鉄を叩くような音が聞こえることがあった。知り合った長の一人に、僕とケンはさりげなくその音について訊ねてみた。
「よくはわからないが、北で起きた戦さの時に鍛冶屋を捕虜にしたと噂されている。クレの剣はそいつに作らせているらしいのだ。ほら、運ばれてくる鉄鉱石や炭の一部があの中に運び込まれるだろう。だが実際にどうやって作っているのかは、クレと兵しか知らないのだ」
土壁の中にはクレと兵、そして鉄の材料を運ぶ際のほんのわずかな人しか入れない。謎を解くのは不可能だった。相槌を打つ僕らに、長は最後に言った。
「あの中で作られた剣の内、出来の良い物は王に献上される。そして王と配下の将軍達が身に付けるのだと言う。将軍とは兵を束ねる役目の猛者さ。そしてこれは内緒の話だが、王に献上される物と同等か、それ以上の剣がクレのものとなるらしい」
「え、そんなことをしたら王が怒って、クレをどうにかしてしまうのではないですか?」
僕が問いかけると長はうなずいた。
「もちろん王に知られたら大事だ。だが、鉄炉の中で行われることを王が知る術はない。それに何といってもクレは王の弟だ。よほどのことが無い限り罰を受けることはないのだ。王としてもこの辺境の地にクレがいる以上、自分の地位を脅かすことはないと安心しているのさ」
驚くべき話だった。鉄炉に来る前に一度だけ目にした王。あのきらびやかな絶対者の弟、王に次ぐ存在、それがクレだというのだ。
その晩の僕らは今後のことについて何一つ思い付くこともなく、ただため息をついていた。いつもはサイの所に行ってしまうソウですら、僕の話を聞いて考え込む様子だった。クレに勝負を挑んで勝つ方法がないかと、ソウなりに考えているのだろう。その時だった。うつむいて座り込む僕らの前に二人の男が足を止めたのだ。そういえば、新たな人々が船で到着したと耳にしていた。立ち止まったままの二人。何だろうと顔を上げると、そこにあったのは懐かしいラウトの笑顔だった。港で離れ離れになったラウト。はるばる鉄炉まで来てくれたのだ。嬉しさと懐かしさに思わず立ち上がろうとしたその時、もう一人の顔を見て、僕らは衝撃を受けた。大きな身体で僕らを見下ろすように立ち、右の口の端を少しだけ持ち上げるようにして、かすかに笑みを浮かべている。離され島で別れて以来、二度と会うこともないと思っていた相手。僕らの前に立つその男は、海賊リキだった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
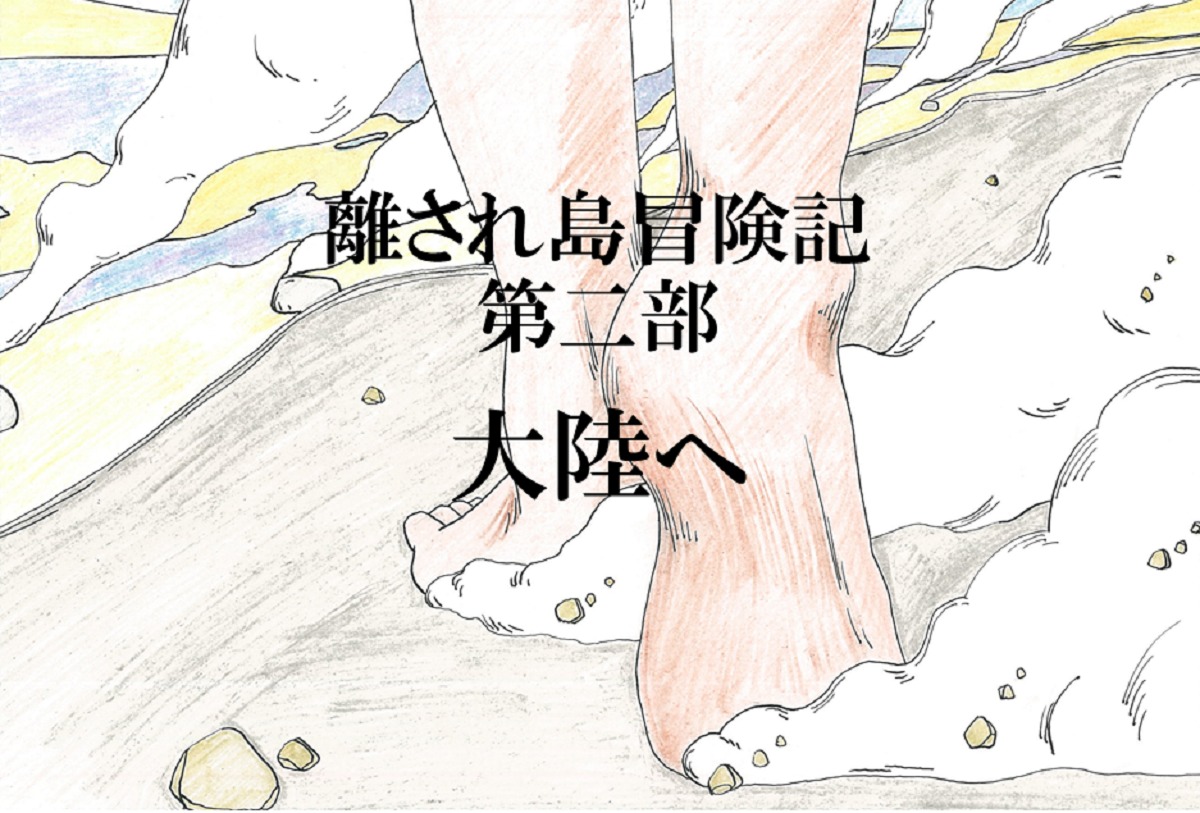

コメント