スポンサーリンク

最初の一手のあと、ケンは手のひらを返して右手の人差し指と中指をじっと見た。
「石を置くって、こういう感触なのだな」
しみじみとした口調で自らに言い聞かせるようにケンはつぶやいた。
「なんだ、お前は本当に白黒を初めてやるのか?」
クレはケンの様子を見て、驚きつつも勝ちを確信したようだった。そして、彼から見て右下の隅、ケンから見て左上に二手目にあたる黒石を置いた。これも実に普通の手だった。三手目、ケンは右下隅に白石を置いた。
白黒は自分の石で囲った陣地と相手から取り上げた石の合算が得点となる。言わば陣地合戦であり、広い所を占有するのが先決なのだ。ところが、初心者はつい相手の石の近くに石を置きたくなるものなのだ。先日のリキのように、すぐに獲った盗られたの勝負に行きたくなる。ところがケンは違った。一番陣地にし易い、右上、左上、右下、左下の隅をしっかり確保しようとしている。村の食料確保の旅、それに続く離され島での生活。たぐい稀なケンの思考力を知ってはいた。けれども、これまで他人の勝負をただ見ているだけだったケンに、果たして白黒勝負ができるものなのか。任せたものの半信半疑だった自分を思い、心の中でケンに頭を下げた。
4手目、クレは初手でケンが置いた石に掛っていった。ケンから見て左下、クレから見て右上にあたる残った一隅に打つかと思っていたが、そうではなかったのだ。相手が掛って来た時に人は平静ではなくなるものだ。僕自身も自分の石の近くに相手の石が来た途端に背中に汗をかき出す経験を幾度もしている。たぶん、クレは初めて白黒勝負をすると言うケンの対応力を見たいと考えたのだろう。そうとすると、この掛かりに対してケンがどう対応して、その後に残った左下の隅にどちらが先着するのかが最初の見所となる。僕であれば、初手の石とでクレの置いた石を挟むように置くのだけれど、ケンはどうするのだろう。
5手目、ケンは空いていた左下隅に白石を置いた。あっさりと、当たり前だろうというように。掛かられるということは目の前に剣抜いた敵が現れたようなものなのだ。並みの人間であれば、自らの剣を抜いて戦うか、加勢を呼びたくなる。ところがケンはそれを無視、空いた隅の方が大事だという。クレの表情が変わった。
「リョウ、何故ケンはそっぽを向いてあんな所に石を置くんだよ?」
ふいに背中を突かれたかと思うと、リキが疑問を囁いてきた。
「こちらの陣地を獲る方が大きい、来るなら来い。ケンはクレに宣戦布告しているのだ」
「最初の石を獲られちまったらどうするのさ?」
リキが問う。
「獲られたらその時点でケンの負けは決まるよ。けれどケンは獲られない自信があって左下に先着した。こいつ、強いかもしれぬ。クレはそう考えているよ、たぶん」
僕は説明になっているような、そうでないような返事をした。白黒勝負観戦の時に、傍らで手を読むような発言をするのはやってはならないものなのだ。時に勝負の行方を左右しかねないからだ。必然的に打ち手の心情をおもんばかることが話の中心になってしまうのは致し方ないことだった。その時、クレが顔を上げてこちらをにらむのがわかった。どうも僕の言ったことは図星だったようだ。しばし、こちらをにらんだ後、今度は右下隅のケンの白石にクレは掛かって行った。まるで、ケンの初手右上隅の石などどうにでも攻略できるとでも言いたげな、自信あふれる手だった。その手を見てケンが首を傾げた。二か所で戦いが始まるのだから確かに悩ましい。選択肢はいくつもある。クレの手に対してそのまま右下隅の石から開く、あるいは挟むも良し、左上隅のクレの石に掛かり返す手もある。何せ序盤、打つ手はいくらでもある。どこを重要視して、また、手を抜くのか。考えが決まったのか、ケンの右手がゆっくりと石に伸びた。そして摘まみ上げられた白石は、よどみのない動きで盤上に打ち据えられた。
「いざとなったら自分達だけで逃げろとリキ親分から言われているんだ」
ガリが言った。ソウ、テラ、コウ、そしてサイの四人は、ガリの道案内で台地をしばらく歩いた後、河まで下って行った。後から来る四人を待つことは止めて、先に船に戻ることにしたのだ。ソウとテラは当初、台地の上で遅れてくる四人を待ちたいと主張した。だが、返ってきた返事はこうだった。
「確かに船の船長達から協力は取り付けた。でもここは大陸だ。いつ裏切りにあってもおかしくない。お前達も痛い目にあっているからわかるだろう。もし船が出航してしまったなら、この広い土地で元来た海まで戻ることなど到底できないぞ」
「でもポンチョが乗っているのだろう?簡単に出航させたりはしないのではないかな?」
ソウの質問にガリは首を横に振った。
「一人だけだと危ういな。数人で襲われたらひとたまりもない。だが、俺が戻って二人、いや、お前を入れて三人となると簡単には裏切られることはない。三人の男を襲うとなれば、裏切る方も痛い目を見るのは確実だからな」
ガリの言葉にソウはうなずいた。ガリから戦い手の一人として認められたのが嬉しい。離され島と共に流されて以来、戦わなければならない状況と言えば、それこそガリ達海賊らが島に上陸した時くらいだ。ずいぶん長い間、のんびりとした気分で生きてきた。しかし、元が村の子供達の中で一番の暴れん坊だったソウなのだ。ガリと話をしている内に頬が微かに紅潮して、いつしか早足になっていた。
「テラ、コウ、サイ、急ごう。船でポンチョが待っている」
ソウは後ろを振り返って三人の少女に声をかけた。いつになく厳しい表情をしているソウに、コウとサイは一瞬怯んで立ち止まった。
「行こう」
テラが二人の背中に手を置いて優しく声をかけた。それを合図に一行の歩みは一気に早くなった。
つづく
第一部は下記リンクから。AMAZON Kindle unlimited会員様は追加料金無しでお読みいただけます。
スポンサーリンク

離され島冒険記 (冒険小説)
一話前に戻る
最初に戻る
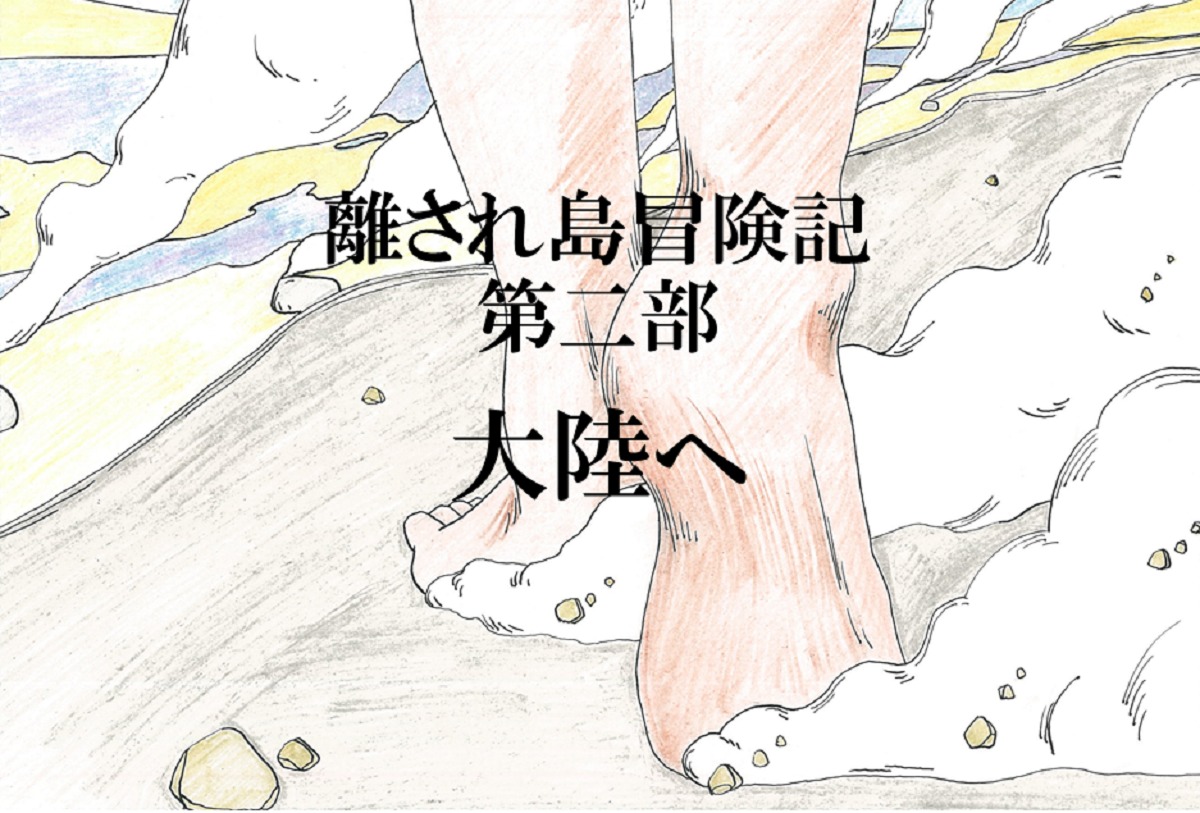

コメント